芥川龍之介
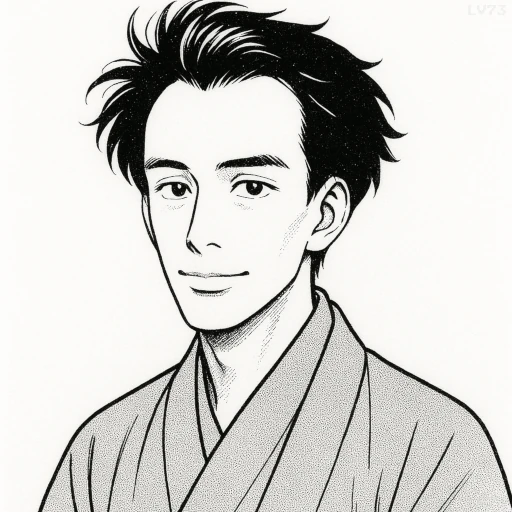
- 1892年3月1日~1927年7月24日
- 日本出身
- 小説家、評論家
人物像と評価
芥川龍之介は、大正時代を代表する小説家であり、日本近代文学における短編の名手として不動の地位を築いた人物である。
初期には古典や歴史題材をもとに『羅生門』『鼻』『地獄変』などを発表し、鋭い人間観察と簡潔な文体で注目を集めた。
晩年には内面の不安や時代の混乱を背景に『河童』『歯車』などの自伝的作品を手がけ、近代知識人の苦悩を深く描き出した。
理知的な文体と象徴性に富む作品群は、教養と技巧の結晶と評される。
一方で、神経衰弱や自己否定の色が強まった晩年には評価が分かれ、1927年に自死したことも含め「近代の不安」の象徴とされた。
それでもなお、その文学的完成度と鋭い文明批評は日本文学史において屈指の存在であり、芥川賞にも名を冠されるなど、後世への影響は極めて大きい。
引用
- 「悪魔は、ころんでも、ただは起きない。誘惑に勝ったと思う時にも、人間は存外、負けている事がありはしないだろうか」
- 「あらゆる言葉は銭のように必ず両面をそなえている。たとえば『敏感な』という言葉の一面は畢竟『臆病な』ということに過ぎない」
- 「あらゆる古来の天才は、我々凡人の手のとどかない壁上の釘に帽子をかけている。もっとも踏み台はなかったわけではない」
- 「あらゆる詩人の虚栄心は言明すると否とを問わず、後代に残ることに終している」
- 「あらゆる東京の中学生が教師につける渾名ほど刻薄に真実に迫るものはない」
- 「ある狂信者のポルトレエ(肖像)ーー彼は皮膚に光沢を持っている。それから熱心に話す時はいつも片目をつぶり、銃でも狙うようにしないことはない」
- 「いかに都会を愛するか?ーー過去の多い女を愛するように」
- 「いわゆる通俗小説とは詩的性格を持った人々の生活を比較的に俗に書いたものであり、いわゆる芸術小説とは必ずしも詩的性格を持っていない人々の生活を比較的詩的に書いたものである」
- 「生まれる時に死を負って来るのはすべての人間の運命だ」
- 「大いなる民衆は滅びない。あらゆる芸術は形を変えても、必ずそのうちから生まれるであろう」
- 「大勢の人々の叫んでいる中に一人の話している声はけっして聞えないと思われるであろう。が、事実上必ず聞えるのである。わたしたちの心の中に一すじの炎の残っている限りは」
- 「臆病は文明人のみの持っている美徳である」
- 「お前の根をしっかりとおろせ。お前は風に吹かれている葦だ。空模様はいつ何時変るかも知れない。ただしっかり踏んばっていろ。それはお前自身のためだ。同時にまたお前の子供たちのためだ。うぬぼれるな。同時に卑屈にもなるな。これからお前はやり直すのだ」
- 「女は女自身、男と生理的及び心理的に違っている点を強調することによってのみ、世の中の仕事に加わる資格ができると思う」
- 「女は情熱に駆られると、不思議にも少女らしい顔をするものである。もっともその情熱なるものはパラソルに対する情熱でもさしつかえない」
- 「女はつねに好人物を夫に持ちたがるものではない。しかし男は好人物をつねに友だちに持ちたがるものである」
- 「革命に革命を重ねたとしても、我々人間の生活は『選ばれたる少数』を除きさえすれば、いつも暗澹としているはずである。しかも『選ばれたる少数』とは『阿呆と悪党と』の異名に過ぎない」
- 「火事はどこか祭礼に似ている」
- 「風のなびいたマッチの炎ほど無気味にも美しい青いろはない」
- 「彼の幸福は彼自身の教養のないことに存している。同時にまた彼の不幸もーーああ、何という退屈さ加減!」
- 「彼はただ薄暗い中にその日暮らしの生活をしていた。いわば刃のこぼれてしまった、細い剣を杖にしながら」
- 「考えれば考えるほど、いよいよ底の知れなくなるものは天下に芸道ただ一つである」
- 「危険なのは技巧ではない。技巧を駆使する小器用さなのだ。小器用さは真面目さの足りない所をごまかしやすい」
- 「軍人は小児に近いものである。英雄らしい身振りを喜んだり、いわゆる光栄を好んだりするのは今更ここに云う必要はない。機械的訓練を貴んだり、動物的勇気を重んじたりするのも小学校にのみ見得る減少である」
- 「芸術家は非凡な作品を作るために、魂を悪魔へ売り渡すことも、時と場合ではやり兼ねない」
- 「結婚は性欲を調節することには有効である。が、恋愛を調節することには有効でない」
- 「公衆の批判は、つねに正鵠を失しやすいものである」
- 「好人物は何よりも先に天上の神に似たものである。第一に歓喜を語るのによい。第二に不平を訴えるのによい。第三にーーいてもいないでもよい」
- 「五欲の克服のみに骨を折った坊主は、偉い坊主になったことを聞かない。偉い坊主になったものは、つねに五欲を克服すべき、他の熱情を抱き得た坊主である」
- 「古来いかに大勢の親はこういう言葉を繰り返したであろう。ーー『わたしは畢竟失敗者だった。しかしこの子だけは成功させなければならぬ』」
- 「古来の女子参政権論者はいずれも良妻を伴っていた」
- 「始終、いじめられている犬は、たまに肉を貰っても容易によりつかない」
- 「自分は大川があるが故に『東京』を愛し、『東京』あるが故に、生活を愛するのである」
- 「社会主義は、理非曲直の問題ではない。単に一つの必然である」
- 「自由とは山巓の空気に似ている。どちらも弱い者には堪えることはできない」
- 「酒色を恣にしている人間がかかった倦怠は、酒色で癒る筈がない」
- 「小説家たらんとするものは自動車学校を卒業せざる運転手の自動車を街頭に駆るがごとし。一生の平穏無事なるを期するべからず」
- 「死を予想しない快楽位、無意味なものはないじゃあないか」
- 「人生苦あり、以て楽しむべし。人間死するあり、以て生くるを知る」
- 「人生に微笑を送るために第一には吊り合いの取れた性格、第二に金、第三に僕よりも逞しい神経を持っていなければならぬ」
- 「人生は一行のボオドレエルにも若かない」
- 「人生は狂人の主催に成ったオリムピック大会に似たものである」
- 「人生は地獄よりも地獄的である」
- 「人生は一箱のマッチに似ている。重大に扱うのはばかばかしい。重大に扱わなければ危険である」
- 「人生は落丁の多い書物に似ている。一部を成すとは称しがたい。しかしとにかく一部を成している」
- 「人生を幸福にするためには、日常の瑣事を愛さなければならぬ」
- 「粗密は気質の差によるものである。粗を嫌い密を喜ぶのは各好む所に従うがよい。しかし粗密と純雑とは、自らまた異なっている。純雑は気質の差のみではない。さらに人格の深処に根ざした、我々が一生の一大事である」
- 「他人を弁護するよりも自己を弁護するのは困難である。疑うものは弁護士を見よ」
- 「だれが御苦労にも恥じ入りたいことを告白小説などに作るものか」
- 「単純さは尊い。が、芸術における単純さというものは、複雑さの極まった単純さなのだ」
- 「敵意は寒気と選ぶ所はない。適度に感ずる時は爽快であり、かつまた健康を保つ上には何びとにも絶対に必要である」
- 「天下に我々の恋人ぐらい、無数の長所をそなえた女性は一人もいないのに相違ない」
- 「天才とは僅かに我々と一歩を隔てたもののことである。ただこの一歩を理解するためには百里の半ばを九十九里とする超数学を知らなければならぬ」
- 「天才の一面は明らかに醜聞を起こし得る才能である」
- 「天才の悲劇は『小ぢんまりした、居心のいい名声』を与えられることである」
- 「どうせ生きているからには、苦しいのはあたり前だと思え」
- 「道徳は常に古着である」
- 「道徳は便宜の異名である。『左側通行』と似たものである」
- 「棘のない薔薇はあっても、受苦を伴わない享楽はない」
- 「なぜ軍人は酒にも酔わずに、勲章を下げて歩かれるのであろう?」
- 「何かものを考えるのによいのはカッフェの一番隅の卓子、それから孤独を感じるのによいのは人通りの多い往来のまん中、最後に静かさを味わうのによいのは開幕中の劇場の廊下、・・・・・・」
- 「女人は我々男子にはまさに人生そのものである。すなわち諸悪の根源である」
- 「人間は、時として、充されるか充されないか、わからない欲望の為に、一生を捧げてしまう」
- 「忍従はロマンティックな卑屈である」
- 「俳優や歌手の幸福は彼らの作品ののこらぬことである。ーーと思うこともないわけではない」
- 「莫迦な女は嫌いです。ことに利巧だと心得ている莫迦な女は手がつけられません」
- 「文芸家たらんとする中学生は、すべからく体操を学ぶこと勤勉なるべし。然らずんばその体格つねに薄弱にして、とうてい生涯の大業を成就せざるものと覚悟せよ」
- 「文章の中にある言葉は辞書の中にある時よりも美しさを加えていなければならぬ」
- 「文章は何よりもはっきり書きたい。頭の中にあるものをはっきり文章に現したい。僕はただそれだけを心がけている」
- 「紛々たる事実の知識はつねに民衆の愛するものである。彼らの最も知りたいのは愛とは何かと言うことではない。クリストは私生児かどうかと言うことである」
- 「文を作らんとするものはいかなる都会人であるにしても、その魂の奥底には野蛮人の一人持っていなければならぬ」
- 「僕自身の経験によれば、最も甚しい自己嫌悪の特色はあらゆるものに嘘を見つけることである。しかもそのまた発見に少しも満足を感じないことである」
- 「僕たちは、時代と場所との制限をうけない美があると信じたがっている」
- 「僕の精神的生活はめったにちゃんと歩いたことはない。いつも蚤のように跳ねるだけである」
- 「僕は医者に容態を聞かれた時、まだ一度も正確に僕自身の容態を話せたことはない。従って嘘をついたような気ばかりしている」
- 「僕は一円の金を貰い、本屋へ本を買いに出かけると、なぜか一円の本を買ったことはなかった。しかし一円出しさえすれば、僕の欲しいと思う本は手にはいるのに違いなかった。僕はたびたび七十銭か八十銭の本を持って来た後、その本を買ったことを後悔していた。それはもちろん本ばかりではなかった。僕はこの心もちの中に中産下級階級を感じている」
- 「僕は屈辱を受けた時、なぜか急には不快にはならぬ。が、彼是一時間ほどすると、だんだん不快になるのを常としている」
- 「僕は象を『可愛いと思うもの』にし、雲を『美しいと思うもの』にした。それは僕には真実だった。が、僕の答案はあいにく先生には気に入らなかった。『雲などはどこが美しい?象もただ大きいばかりじゃないか?』。先生はこうたしなめた後、僕の答案へ×印をつけた」
- 「僕はたびたび他人のことを死ねばよいと思ったことがある。そのまた死ねばよいと思った中には僕の肉親さえいないことはない」
- 「僕はどういう良心も、ーー芸術的良心さえ持っていない。が、神経は持ち合わせている」
- 「僕は肥った人の手を見ると、なぜか海豹の鰭を思い出している」
- 「僕は僕の住居を離れるのに従い、何か僕の人格もあいまいになるのを感じている。この現象が現れるのは僕の住居を離れること、三十マイル前後に始まるらしい」
- 「僕は見知り越しの人に会うと、必ずこちらからおじぎをしてしまう。従って向こうの気づかずにいる時には『損をした』と思うこともないではない」
- 「僕は未知の女から手紙か何か貰った時、まず考えずにいられぬことはその女の美人かどうかである」
- 「僕はめったに憎んだことはない。その代りには時々軽蔑している」
- 「僕は憂鬱になり出すと、僕の脳髄の襞ごとに虱がたかっているような気がしてくるのです」
- 「僕らの性格は不思議にもたいてい頸すじの線に現れている。この線の鈍いものは敏感ではない」
- 「僕らが独創と呼ぶものは僅かに前人の跡を脱したのに過ぎない。しかもほんの一歩ぐらい、ーーいや、一歩でも出ているとすれば、たびたび一時代を震わせるのである」
- 「民衆の愚を発見するのは必ずしも誇るに足ることではない。が、我々自身もまた民衆であることを発見するのはともかくも誇るに足ることである」
- 「もし正直になるとすれば、我々は忽ち何びとも正直になられぬことを見出すであろう。この故に我々は正直になることに不安を感ぜずにはいられぬのである」
- 「もし天国を造り得るとすれば、それはただ地上にだけである。この天国はもちろん茨の中に薔薇の花の咲いた天国であろう」
- 「最も文芸的な文芸は僕らを静かにするだけである。僕らはそれらの作品に接した時には恍惚となるよりほかにしかたはない」
- 「最も僕を憂鬱にするもの。ーーカアキイ色に塗った煙突。電車の通らない通路の錆び。屋上庭園に飼われている猿」
- 「夜半の隅田川は何度見ても、詩人S・Mの言葉を越えることは出来ない。ーー『羊羹のように流れている』」
- 「庸才の作品は大作にもせよ、必ず窓のない部屋に似ている。人生の展望は少しも利かない」
- 「輿論は常に私刑であり、私刑はまた常に娯楽である。たといピストルを用うる代りに新聞の記事を用いたとしても」
- 「理性のわたしに教えたものは畢竟理性の無力だった」
- 「理想的兵卒はいやしくも上官の命令には絶対に服従しなければならぬ。絶対に服従することは絶対に責任を負わぬことである。すなわち理想的兵卒はまず無責任を好まなければならぬ」
- 「良心は道徳を造るかも知れぬ。しかし道徳はいまだかつて、良心の良の字も造ったことはない」
- 「恋愛の徴候の一つは彼女に似た顔を発見することに極度に鋭敏になることである」
- 「恋愛の徴候の一つは彼女は過去に何人の男を愛したか、或はどういう男を愛したかを考え、その架空の何人かに漠然とした嫉妬を感ずることである」
- 「恋愛はただ性欲の詩的表現を受けたものである。少くとも詩的表現を受けない性欲は恋愛と呼ぶに価しない」
- 「わたしはずいぶん嫉妬深いと見えます。たとえば宿屋に泊った時、そこの番頭や女中たちがわたしに愛想よくおじぎをするでしょう。それからまたほかの客が来ると、やはり前と同じように愛想よくおじぎをしているでしょう。わたしはあれを見ていると何だか後から来た客に反感を持たずにはいられないのです」ーーそのくせ僕にこう言った人は僕の知っている人々のうちでも一番温厚な好紳士だった。
- 「わたしはどんなに愛していた女とでも一時間以上話しているのは退屈だった」
- 「わたしは不幸にも知っている。時には嘘による外は語られぬ真実もあることを」
- 「我々に武器を執らしめるものはいつも敵に対する恐怖である。しかもしばしば実在しない架空の敵に対する恐怖である」
- 「我々日本人の二千年来君に忠に孝だったと思うのは猿田彦命もコスメ・ティックをつけていたと思うのと同じことである。もうそろそろありのままの歴史的事実に徹して見ようではないか?」
- 「我々の機関車を見るたびにおのずから我々自身を感ずるのは必ずしもわたしに限ったことではない。斎藤緑雨は箱根の山を越える機関車の『ナンダ、コンナ山、ナンダ、コンナ山』と叫ぶことを記している」
- 「我々の自己欺瞞は一たび恋愛に陥ったが最後、最も完全に行われるのである」
- 「我々の内部に生きるものを信じようではないか。そうして、その信ずるものの命ずるままに我々の生き方を生きようではないか」
- 「我々はいったい何のために幼い子供を愛するのか?その理由の一半は少くとも幼い子供にだけは欺かれる心配のないためである」
- 「我々を走らせる軌道は、機関車にはわかっていないように我々自身にもわかっていない。この軌道もおそらくはトンネルや鉄橋に通じていることであろう」
- 「我々を恋愛から救うものは理性よりもむしろ多忙である。恋愛もまた完全に行われるためには何よりも時間を持たなければならぬ。ウェルテル、ロミオ、トリスタンーー古来の恋人を考えて見ても、彼らはみな閑人ばかりである」