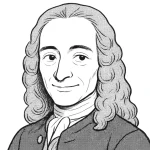「逐語訳をする者たちには災いあれ。すべての言葉をそのまま訳すことで、意味を弱めてしまうのだから!まさにこうして、『文字は殺し、精神は生かす』と言えるのだ」

- 1694年11月21日~1778年5月30日(83歳没)
- フランス出身
- 哲学者、文学者、歴史家
英文
“Woe to the makers of literal translations, who by rendering every word weaken the meaning! It is indeed by so doing that we can say the letter kills and the spirit gives life.”
日本語訳
「逐語訳をする者たちには災いあれ。すべての言葉をそのまま訳すことで、意味を弱めてしまうのだから!まさにこうして、『文字は殺し、精神は生かす』と言えるのだ」
出典
出典不詳(編集中)
解説
ヴォルテールは、逐語訳が原文の意図や精神を損ない、言葉の真の意味を弱めてしまうと批判している。彼は、翻訳においては言葉そのものではなく、原文の背後にある意図やニュアンスを伝えることが重要だと考えていた。「文字は殺し、精神は生かす」という言葉を引用することで、形式にとらわれた翻訳が原作のエッセンスを失わせてしまうという警告を込めている。18世紀のヴォルテールの時代においても、文学や哲学の翻訳は重要であり、その正確性と芸術性が求められていた。
現代においても、この言葉は翻訳やコミュニケーションにおいて「精神を伝えること」の重要性を教えている。たとえば、ビジネスや国際的なやり取りでは、逐語訳が逆に誤解を生むことがあり、内容や意図を柔軟に解釈し、伝える力が必要とされる。文学や詩においても、逐語訳では表現の美しさやニュアンスが失われ、作品の意図が正しく伝わらなくなることがある。ヴォルテールの言葉は、翻訳や解釈が単なる言葉の置き換えではなく、深い理解と共感に基づくものでなければならないことを示している。
この名言は、表面上の言葉にとらわれず、言葉の背後にある真の意味や精神を伝える重要性を教えている。形式に忠実であることも大切だが、それだけに固執すると、言葉の力が失われてしまう。ヴォルテールの言葉は、内容や精神の伝達を重視し、言葉の本質に忠実であることの意義を私たちに思い出させてくれる。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?