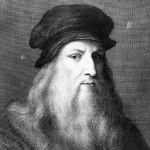「ある動物は大声で鳴き、ある動物は静かで、また別の動物は声を持つが、言葉に近い音を発するものもあれば、そうでないものもいる。音を立てる動物も静かな動物もおり、音楽的なものも非音楽的なものもあるが、多くの動物は繁殖期になると特に騒がしくなる」

- 紀元前384年~紀元前322年
- 古代ギリシャのマケドニア出身
- 哲学者・科学者で学園「リュケイオン」の設立者
- プラトンの弟子で、論理学、生物学、政治学、倫理学などにおいて体系的な知識を構築し、西洋の思想や科学の発展に大きな影響を与えた
英文
”Some animals utter a loud cry. Some are silent, and others have a voice, which in some cases may be expressed by a word; in others, it cannot. There are also noisy animals and silent animals, musical and unmusical kinds, but they are mostly noisy about the breeding season.”
日本語訳
「ある動物は大声で鳴き、ある動物は静かで、また別の動物は声を持つが、言葉に近い音を発するものもあれば、そうでないものもいる。音を立てる動物も静かな動物もおり、音楽的なものも非音楽的なものもあるが、多くの動物は繁殖期になると特に騒がしくなる」
解説
この言葉は、動物の声や発声の多様性についてアリストテレスが述べたものである。彼は、動物がそれぞれ異なる方法で声を発し、その声にはさまざまな特徴があることを観察した。ある動物は大声を発し、ある動物は沈黙を保ち、また他の動物は人間のように単語に似た発声ができる場合もあると述べている。さらに、動物たちの多くが特に繁殖期になると賑やかに鳴く傾向があることも指摘し、これは動物の本能的なコミュニケーションや行動パターンに関係していると考えられる。
アリストテレスは、動物の声の種類や発声の違いが生態や種ごとの特性に基づいていることに注目している。彼は、鳴き声の有無や声の大きさ、音楽的なリズムの有無といった発声パターンが、動物の種ごとに異なるだけでなく、特定の時期(特に繁殖期)に応じて変化することを理解していた。動物はこの声を用いて仲間とのコミュニケーションや警戒、求愛などを行うため、それぞれの声には種に固有の目的があると考えられる。
具体例として、鳥のさえずりやライオンの咆哮が挙げられる。鳥は特に繁殖期に美しいさえずりを奏で、仲間やパートナーにメッセージを伝える。ライオンはその領域を知らせるために大きな声で咆哮し、威厳を示す。こうした発声は、動物が仲間や他の動物に意図を伝えるための重要な手段であり、種の生存や繁殖に役立っている。また、イルカやクジラの鳴き声も、音を使ったコミュニケーションの一例であり、音波を用いて他の個体とやり取りすることで、群れの結束を保っている。
現代においても、アリストテレスのこの考え方は動物行動学において意義がある。動物の鳴き声が種の生態や生存にどのように役立っているのかを理解することで、動物のコミュニケーションや生態系のバランスをより深く知ることができる。音を使ったコミュニケーションは、動物が生きるための適応であり、環境や繁殖期に応じた賑やかさが観察されることは、アリストテレスの観察の正しさを示している。
アリストテレスのこの言葉は、動物の声やコミュニケーションが持つ多様性とそれが果たす役割について教えている。鳴き声や音を用いた動物の行動は、種ごとに異なるだけでなく、繁殖期などの特定のタイミングで重要性が増す。これにより、動物たちは種の存続や群れの結束を維持しており、この多様性が生態系における生命の豊かさを象徴しているといえる。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?