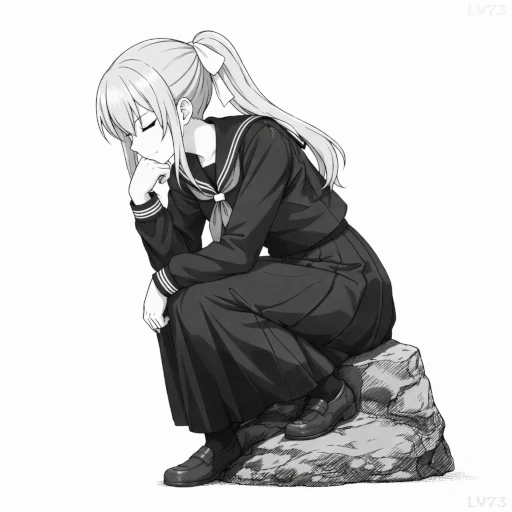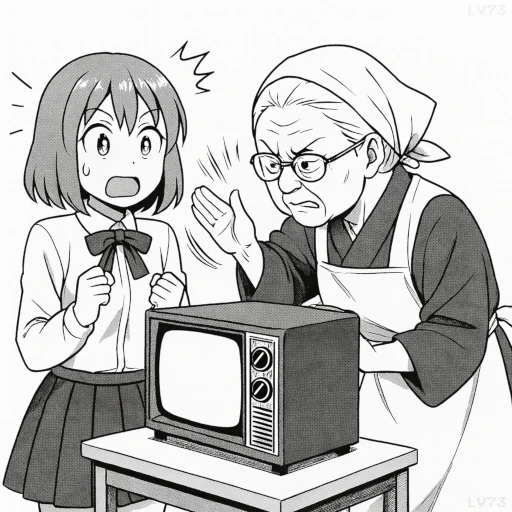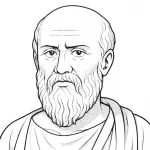「自らの理性の働きによって生じたものでない徳を持つ存在を徳あると呼ぶのは、実際には茶番です」

- 1759年4月27日~1797年9月10日(38歳没)
- イギリス出身
- 作家、哲学者
英文
“In fact, it is a farce to call any being virtuous whose virtues do not result from the exercise of its own reason.”
日本語訳
「自らの理性の働きによって生じたものでない徳を持つ存在を徳あると呼ぶのは、実際には茶番です」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、徳とは理性に基づいて初めて本物となるという思想を示している。18世紀の社会では、女性に対して従順や純潔といった「徳」が強調されたが、それはしばしば教育や自立を奪った結果として生じた受動的なものだった。著者はそのような徳を否定し、自らの思考と判断によって形成された徳こそが真の価値を持つと主張したのである。
この立場は、当時の宗教的・社会的規範に挑戦するものであった。人が善良に見える行動をしていても、それが単なる慣習や強制から生じたのなら、そこには主体性が欠けている。したがって、それを「徳」と呼ぶのは虚偽であり茶番であるという強い批判が込められている。
現代においても、この視点は大きな意義を持つ。例えば社会的な圧力や形だけのモラルに従うのではなく、自ら考え抜いた上で行動することが本当の倫理的価値につながる。環境問題や人権問題などの課題においても、主体的に判断し行動することが求められており、この名言はその重要性を鋭く指摘しているのである。
「メアリ・ウルストンクラフト」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!