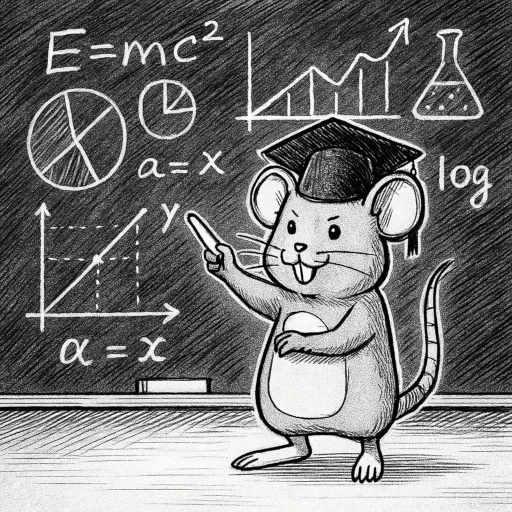「ドイツの物理学者たちは、原子爆弾の製造と構造について少なくとも十分な知識を持っていたので、戦争中にドイツで爆弾を製造することは不可能であると理解していた。そのため、彼らは原子爆弾を作るべきかどうかという道徳的決断を迫られることはなく、ただウラン機関の研究にのみ従事していた」

- 1901年12月5日~1976年2月1日(74歳没)
- ドイツ出身
- 物理学者、ノーベル物理学賞受賞者
英文
“The German physicists knew at least so much about the manufacture and construction of atomic bombs that it was clear to them that the manufacture of bombs in Germany could not succeed during the war. For this reason, they were spared the moral decision whether they should make an atomic bomb, and they had only worked on the uranium engine.”
日本語訳
「ドイツの物理学者たちは、原子爆弾の製造と構造について少なくとも十分な知識を持っていたので、戦争中にドイツで爆弾を製造することは不可能であると理解していた。そのため、彼らは原子爆弾を作るべきかどうかという道徳的決断を迫られることはなく、ただウラン機関の研究にのみ従事していた」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、戦時下のドイツにおける原子力研究の実態と、その倫理的側面を説明している。ハイゼンベルクをはじめとするドイツの物理学者たちは、原子爆弾の理論的可能性を知りつつも、当時の技術的・資源的制約から、短期間での実現は不可能だと判断していた。したがって、彼らはアメリカのマンハッタン計画のように大規模な兵器開発へと踏み込むことはなく、原子炉(ウラン機関)の研究に留まった。
ここで重要なのは、倫理的選択の回避である。もしドイツに十分な資源や時間があったなら、物理学者たちは爆弾製造に協力するか否かという深刻な決断を迫られただろう。しかし、実際には不可能と分かっていたため、彼らは「決断せずに済んだ」という形で戦後を振り返っている。この言葉には、自己弁護的な側面があると同時に、科学者が歴史的状況によって倫理的負担を免れることもあるという現実が映し出されている。
現代において、この言葉は科学と倫理の関係を考える上で示唆的である。技術的限界が倫理的ジレンマを和らげることもあるが、逆に技術が進歩した現代では、科学者はより直接的に責任を問われる。核兵器やAI、バイオテクノロジーといった分野において、研究者は「可能だからやる」のではなく、可能であってもやるべきかどうかを問う責任を持つ。この言葉は、その歴史的背景とともに、科学者倫理の永遠の課題を示している。