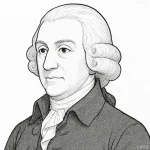「その構成員の大多数が貧しく惨めであるような社会が、繁栄し幸福であるはずがない」
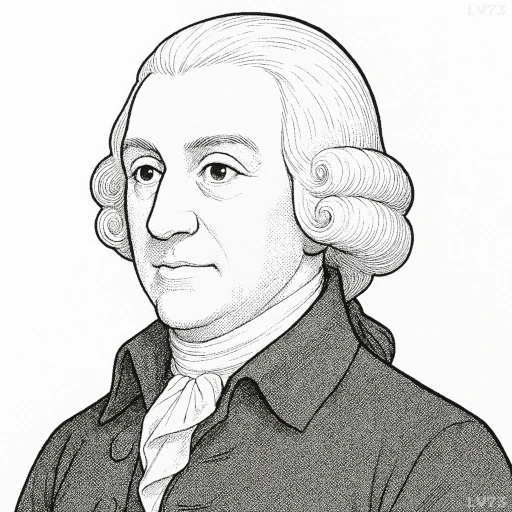
- 1723年6月5日~1790年7月17日(67歳没)
- スコットランド出身
- 経済学者、哲学者、「古典派経済学の父」
英文
“No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.”
日本語訳
「その構成員の大多数が貧しく惨めであるような社会が、繁栄し幸福であるはずがない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉はアダム・スミスが社会全体の繁栄と平等の関係を指摘したものである。彼は個人の利益追求が市場を通じて社会に富をもたらすと論じたが、その恩恵がごく一部に偏るならば、真の意味での繁栄は成立しないと考えた。すなわち、国の富は単なる総量ではなく、社会構成員の生活水準に左右されるという洞察である。
この思想は18世紀の急速な経済発展と格差の拡大という現実を背景としている。スミスは、労働者が極端に貧しい状態に置かれるならば、社会秩序は不安定化し、生産力も低下することを見抜いていた。つまり、社会の幸福は国民多数の生活向上に依存するという考えを強調したのである。
現代においても、この言葉は強い意義を持つ。経済成長が一部の富裕層に集中し、格差が拡大すれば、社会の安定や幸福は損なわれる。貧困対策や社会保障制度の必要性は、このスミスの洞察を裏付けている。彼の言葉は、持続的な繁栄には広範な生活の向上が不可欠であるという普遍的な教訓を示している。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「アダム・スミス」の前後の名言へ
申し込む
0 Comments
最も古い