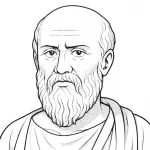「最も徳の高い人とは、徳を持ちながらも、それを見せびらかそうとしない人である」

- 紀元前427年~紀元前347年
- 古代ギリシアのアテナイ(アテネ)出身
- 哲学者、学者、アカデメイア(アカデミー)創設者
英文
“The most virtuous are those who content themselves with being virtuous without seeking to appear so”
日本語訳
「最も徳の高い人とは、徳を持ちながらも、それを見せびらかそうとしない人である」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、真の美徳は他人に見せつけるものではなく、自分の内面から自然に発せられるものであるという考えを表している。プラトンは、徳を持つ人は、自分が善良であることを他人に誇示したり、評価を得るために行動するのではなく、自分の信念に従って静かに徳を実践するべきだと考えていた。真の美徳は無私のものであり、外見や他者からの称賛を求めることなく、自らの行動に満足できる精神性を持つことが大切だというメッセージが、この言葉に込められている。
この考えは、外見や他人の評価に左右されることの危険性を指摘している。多くの人は、他者に良く思われたい、賞賛されたいという欲望から、善行を行うことがある。しかし、プラトンは、そのような行動は真の美徳ではないと考えた。美徳を持つこと自体に満足し、他人の目を気にせずに善を行う人こそが、本当に徳の高い人である。たとえば、慈善活動をする際に自分の行いを誇示する人よりも、静かに他人を助け、自分の善行を広めようとしない人の方が、より高い倫理的価値を持つとされる。見返りを求めずに善を行うことが、本物の徳を体現することであると、プラトンは主張している。
現代社会においても、この名言は重要な意味を持つ。私たちはしばしば、社会的な評価や他人の承認を求めて行動するが、それが本当の善行や美徳であるとは限らない。特に、ソーシャルメディアの普及により、他人に自分の良さをアピールする行動が増えている。しかし、プラトンの言葉は、善行は人に見られるために行うのではなく、自分の価値観や信念に基づいて行うべきだと教えている。たとえば、環境保護のための活動やボランティアに参加する場合、その行動の目的が他者からの評価を得ることではなく、純粋な善意から来ているかどうかを見極めることが重要である。本物の美徳は、見せかけではなく、内面から生まれるものである。
「プラトン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!