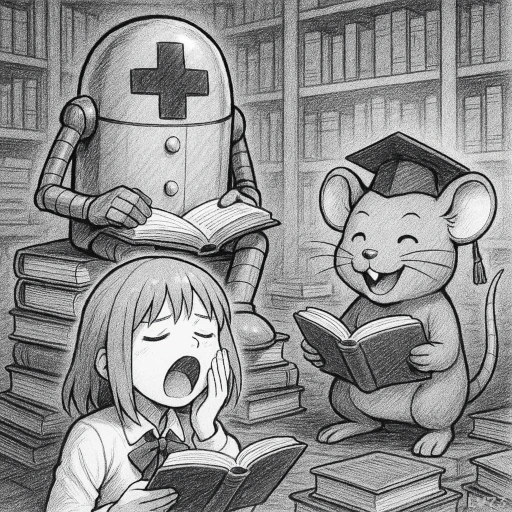「強制されて得た知識は、心にしっかりと根付くことはない」

- 紀元前427年~紀元前347年
- 古代ギリシアのアテナイ(アテネ)出身
- 哲学者、学者、アカデメイア(アカデミー)創設者
英文
“Knowledge which is acquired under compulsion obtains no hold on the mind”
日本語訳
「強制されて得た知識は、心にしっかりと根付くことはない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、学びが自発的でなければ、本当に心に根付くことはないというプラトンの教育哲学を表している。知識を学ぶ際に強制や圧力によって得たものは、長期的に持続することが難しく、本質的な理解や応用が身につかないという指摘だ。プラトンは、学びが効果的であるためには、興味や好奇心と結びついていなければならないと考えていた。人間は、自ら学びたいと思うときに初めて、知識を深く理解し、意味のある形で保持することができるのである。
プラトンのこの考えは、教育の方法論や動機付けの重要性に関するものでもある。強制的に暗記させたり、試験のためだけに知識を詰め込む教育は、生徒の理解を深めることが難しい。むしろ、自主的な学びが奨励される環境では、生徒は自ら考え、疑問を持ち、探求することで、より深く知識を定着させることができる。たとえば、子どもが科学に興味を持った場合、強制的に理論を学ぶのではなく、実験や観察を通じて自分で探求することで、学びが自然に深まる。学びは強制ではなく、興味と探求心によって最も効果的に進むという考えは、現代の教育にも影響を与えている。
現代の教育システムにおいても、この哲学は非常に有用である。多くの教育者は、学生の興味を引き出し、学びを楽しいものにすることで、知識がより深く定着することを目指している。たとえば、プロジェクトベースの学習や、探究型の学習プログラムは、自主的な学びを促進し、生徒が主体的に問題を解決する力を育むことを目的としている。学習の過程で自らの好奇心を満たす経験は、知識が単なる情報から実用的で生きた知識に変わる。学びを自発的に行うことで、知識は単なる記憶に留まらず、深い理解へと発展する。
「プラトン」の前後の名言へ
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!