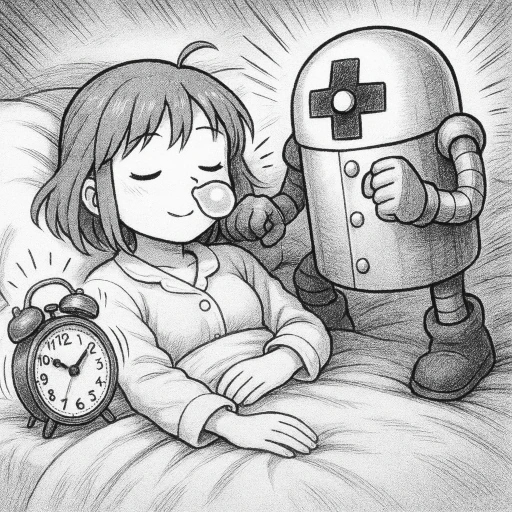「いたずら好きな人々、害をなす人々は常に存在してきた。ここ数千年ずっとそうだったし、未来にもそうだろう」

- 1935年7月6日~
- チベット出身
- 宗教指導者、仏教僧、チベット亡命政府の元首相・精神的指導者
英文
“Some mischievous people always there. Last several thousand years, always there. In future, also.”
日本語訳
「いたずら好きな人々、害をなす人々は常に存在してきた。ここ数千年ずっとそうだったし、未来にもそうだろう」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、人間社会における「完全な善」の不可能性と、悪意や混乱をもたらす存在の恒常性を認めた、達観した視点からの発言である。ダライ・ラマ14世は、慈悲と非暴力を説く一方で、現実の世界には常に利己的、破壊的、混乱をもたらす人々が存在することを否定していない。このような存在を「mischievous people(いたずら好きな人々)」という比較的柔らかな表現で語ることで、怒りや憎しみではなく、理解と冷静な認識を促している点が印象的である。
「last several thousand years, always there」という言い回しには、人間の歴史において悪意が例外ではなく常態であるという洞察が込められている。つまり、理想的な社会を追求することは重要だが、悪意ある行動が完全になくなることはなく、それを前提とした忍耐と知恵が必要であるという現実主義的な倫理観を示している。
この名言は、理想と現実のバランスをどう保つかという問題に対するひとつの答えでもある。善意を信じながらも、悪意の存在を否定せず受け入れるという姿勢は、持続可能な共生社会を築くための精神的柔軟性を象徴している。理不尽や妨害に直面したときでも、「こういう人は常にいるものだ」と受け止め、冷静さを保つための智慧が、この短い言葉に凝縮されている。
「ダライ・ラマ14世」の前後の名言へ
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!