ダライ・ラマ14世

- 1935年7月6日~
- チベット出身
- 宗教指導者、仏教僧、チベット亡命政府の元首相・精神的指導者
人物像と評価
ダライ・ラマ14世(法名:テンジン・ギャツォ)は、チベット仏教の最高指導者であり、宗教的精神性と政治的指導力を併せ持つ人物である。
1940年に即位し、1950年に中華人民共和国によるチベット侵攻を受けた後も、1959年にインドへ亡命してからはチベット亡命政府の長として民主的改革とチベット民族の自由を訴え続けた。
彼の功績は、非暴力と対話による問題解決を国際社会に訴えたことにある。
1998年にはノーベル平和賞を受賞し、宗教間対話、人権、環境問題など幅広い分野で世界的影響力を持つ精神的リーダーとなった。
また、慈悲と共感を説く仏教哲学を、宗教を越えた普遍的価値として広めている。
ダライ・ラマ14世は信仰・哲学・平和運動の象徴として、世界中から尊敬を集める存在である。
「いいね」
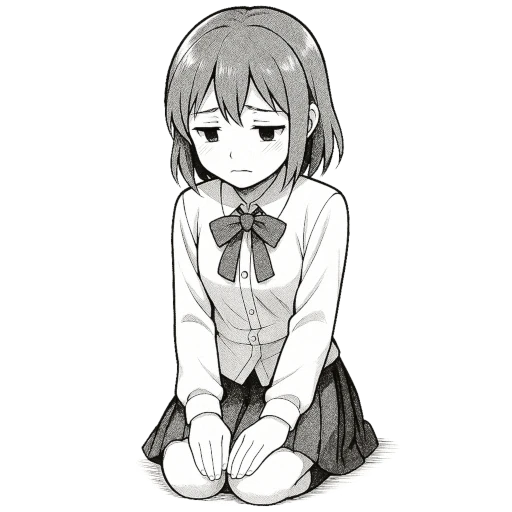
「いいね」が足りてない…
引用
- 「意見の相違は普通のことである」
- 「私自身の転生に関してはっきりさせておきたいのは、その最終的な権限は他の誰でもなく、私自身にあるということだ。中国共産党など論外である」
- 「多くのチベット人が命を犠牲にしている」
- 「人々を暴力で長期的に抑圧し続けることは困難である。これはソ連や東欧諸国の例が示している」
- 「より思いやりのある心、他者の幸福を気づかう意識こそが幸福の源である」
- 「私はただ純粋な精神的指導者でありたいのだ」
- 「世界は人類に属するものであり、この指導者やあの指導者、あるいは王や王子、宗教的指導者のものではない。世界は人類に属するのだ」
- 「幸福とはあらかじめ出来上がったものではない。それは自らの行動によって生まれるのだ」
- 「私の宗教はとても単純だ。私の宗教は思いやりである」
- 「もしできるなら他者を助けなさい。もしそれができないなら、せめて害を与えないようにしなさい」
- 「古い友は去り、新しい友が現れる。それは日々と同じだ。古い一日が過ぎ、新しい一日がやって来る。重要なのは、それを意味あるものにすることだ──意味ある友、あるいは意味ある一日を」
- 「今日では、異なる民族や異なる国家が常識の力によって結びついている」
- 「私の目標は、真の友情によって幸福な社会を築くことだ。チベット人と中国人の間の友情は極めて重要である」
- 「一般的に言って、人間がまったく怒りを見せないなら、何かがおかしいと思う。頭の働きが正常ではないのだ」
- 「私は、焼身自殺そのものも非暴力の実践の一つだと思う。彼らは簡単に爆弾などを使って、多くの人を巻き込むこともできた。だがそうはせず、自分の命だけを犠牲にした。だからこれもまた、非暴力の実践の一部なのだ」
- 「いたずら好きな人々、害をなす人々は常に存在してきた。ここ数千年ずっとそうだったし、未来にもそうだろう」
- 「拷問や暴力を受けたチベット人難民の個人的な話を聞くと、私はときどき悲しみを感じる。いくらか苛立ちや怒りも湧いてくる。だが、それは長くは続かない。私はいつも、より深い次元で考え、慰めの道を探そうと努めている」
- 「心を開いた人々は仏教に関心を持ちやすい。なぜなら仏陀は、ただ信じよと命じるのではなく、物事をよく調べるようにと勧めたからだ」
- 「宗教を信じるか否か、生まれ変わりを信じるか否かにかかわらず、思いやりと慈悲を好まない人はいない」
- 「私は政治的責任を切り離さねばならないと感じた。ダライ・ラマがその重荷を背負うべきではない。だからそれが私の利己的な理由──古きダライ・ラマの伝統を守るためなのだ。政治に関与しないほうが安全なのだ」
- 「最終的な拠り所は常に、個人自身の理性と批判的思考に置かれねばならない」
- 「性別の平等に関する仏教の基本的立場は、古くから存在する。最高位のタントラの段階においても、最も深遠な秘教のレベルにおいても、女性を──すべての女性を──尊重しなければならない」
- 「私が権限を委譲したいと願うのは、責任を回避したいからではない」
- 「死とは衣服を着替えるようなものだ。衣服が古くなれば、時が来て着替える。同じように、この身体も老いれば、時が来て新しい若い身体をまとうのだ」
- 「私は眠るのに何の問題もない」
- 「私はいつも、王や公的な指導者による統治は時代遅れだと考えている。今こそ私たちは現代の世界に追いつかなければならない」
- 「これが私のシンプルな宗教だ。寺院は必要ない。複雑な哲学も必要ない。私たち自身の脳と心が寺院であり、その哲学は思いやりなのだ」
- 「私はいつも、人々に宗教機関と政治機関は分離すべきだと言っている。だがその一方で、自分自身はそれらを結びつけたままにしていた。偽善だ!」
- 「一般的に、民主主義国の政治家がいつも深く物事を考えているとは思わない。時として少し近視眼的だ。彼らは主に次の選挙の票を気にしているのだ」
- 「私は現代の教育制度について常にこう考えてきた。知能の発達には注意を払うが、思いやりの心の育成については当然のこととして軽視されているのだ」
- 「私は自分のことを、ただの一介の仏教僧だと表現している。それ以上でも、それ以下でもない」
- 「ダライ・ラマとは、チベットにおける一時的な指導者にすぎない」
- 「前向きな行動を実現するには、ここに前向きなビジョンを育まねばならない」
- 「すべての宗教は人々のためになろうと努めており、その根本的なメッセージは共通している──愛と慈悲、正義と誠実、そして満足の大切さである」
- 「無知が私たちの支配者である限り、本当の平和が実現する可能性はない」
- 「ダライ・ラマに奇跡の力があると信じたり思ったりする人がいるなら、それはまったくのナンセンスだ。私はただの一人の人間にすぎない」
- 「私たちの人生の目的は、幸せになることである」
- 「中国は世界の潮流に従わねばならない。それはすなわち、民主主義、自由、個人の権利である。遅かれ早かれ中国もその道を進まざるをえない。後戻りはできないのだ」
- 「人間である以上、怒りは心の一部だ。苛立ちもまた心の一部だ。しかし、それは訪れては去っていくものにできる。怒りを心の奥に留めておいてはならない──そうすると多くの疑念、不信、否定的な感情、さらには不安までもが生まれてしまう」
- 「一部の科学者は、気候変動が北極の前例のない氷の融解を引き起こしており、それが極めて不安定な気象パターンに影響していると考えている。私は、そうした科学者や専門家の声に耳を傾けるべきだと思う」
- 「透明性の欠如は、不信と深い不安感を生む」
- 「重要なのは、人が人生に目的を持つことだ。その目的は、有益で、善きものであるべきだ」
- 「私は、21世紀がより幸福な時代になるあらゆる理由があると考えている」
- 「できるかぎり良い態度と良い心を育むことが非常に大切だ。そこから、短期的にも長期的にも、自分にも他人にも幸福がもたらされる」
- 「私は自分自身を、人々のための自由な代弁者だと考えている」
- 「人間の世界におけるあらゆる問題を解決する最良の方法は、すべての当事者が席につき、話し合うことである」
- 「愛と慈悲は贅沢品ではなく、必要不可欠なものである。それなしでは人類は生き残ることができない」
- 「たとえ身体的に困難な状況にあっても、私たちはとても幸せでいられることがある」
- 「私は志願してダライ・ラマになったわけではない」
- 「コンピューターにはまったくお手上げで、頭が真っ白になる」
- 「他人を幸せにしたいなら、思いやりを実践しなさい。自分が幸せになりたいなら、やはり思いやりを実践しなさい」
- 「物事をあらゆる角度から見なさい。そうすれば、あなたはもっと心を開けるようになる」
- 「私たちは皆ともに生きていかなければならないのだから、どうせなら幸せに共に生きようではないか」
- 「すべての主要な宗教伝統は基本的に同じメッセージを持っている。それは愛と思いやり、そして赦しである。重要なのは、それらが私たちの日常生活の一部となることである」
- 「仏教には瞑想など、誰でも取り入れることができる技法がある。そしてもちろん、信仰心や思いやり、赦す力を育むために、すでに仏教の方法を用いているキリスト教の修道士や修道女もいる」
- 「私の信仰は、そのような否定的な感情を克服し、心の均衡を取り戻す助けとなる」
- 「もし私がラサに留まっていたならば、中国の占領がなかったとしても、おそらく正統的な形で儀礼的な役割を担っていたであろう」
- 「夢の中でさえ、自分がダライ・ラマであるとは夢にも思わなかった」
- 「感謝の心を実践するとき、他者に対する敬意が生まれる」
- 「自分が貢献したと思うことが一つある。それは仏教の学と現代科学を結びつけることを助けたことである。他の仏教徒にはそれをした者はいない。他のラマたちは現代科学に注意を払ったことがないと思う。私は子どもの頃から強い関心を持っていた」
- 「不満であるとき、人は常にもっと、もっと、もっとと求める。その欲望は決して満たされることはない。しかし満足を実践するとき、『ああ、私は本当に必要なものはすでにすべて持っている』と自分に言うことができる」
- 「自らの可能性を認識し、自らの能力への自信を持つことで、人はより良い世界を築くことができる」
- 「私が生きている限り、チベット人と中国人との友好に全力を尽くす。そうでなければ意味がない」
- 「寺院は必要ない。複雑な哲学も必要ない。私の寺院は私の脳と心であり、私の哲学は優しさである」
- 「寛容を実践するにあたり、敵こそが最良の教師である」
- 「睡眠は最良の瞑想である」
- 「技術は確かに人間の能力を高めたと思う。しかし技術は思いやりを生み出すことはできない」
- 「どこへ行き人々と会うにしても、人間の価値を広め、調和のメッセージを広めることが最も重要である」
- 「私は常に、人々は宗教を急いで変えるべきではないと言っている。自らの信じる宗教の中に必要な精神的資源を見いだすことには本当の価値がある」
- 「特定の信仰や宗教を持っているなら、それは良いことである。しかし、それがなくても生きていくことはできる」
- 「宗教はいかなる宗教であれ、どれほど素晴らしいものであっても普遍的になることはない。しかし今や教育は普遍的である。ゆえに、幼稚園から大学に至るまでの教育制度を通じて、良きもの、すなわち価値や内なる価値への自覚を育む方法を見つけなければならない」
- 「私はただの一介の仏教僧である。それ以上でも、それ以下でもない」
- 「ダライ・ラマが亡くなればチベットの闘いは消滅し、チベットには希望がなくなるという見解には、私は全く同意しない」
- 「動物でさえ、本当の愛情を示せば、次第に信頼が育まれる……。いつも嫌な顔をして叩いているなら、どうして友情を築けるだろうか」
- 「見かけは絶対的なもののように見えるが、現実はそうではない。すべては相互依存しており、絶対的なものではない」
- 「それを仏教と呼ぶか、他の宗教と呼ぶかにかかわらず、大切なのは自律である。結果を自覚したうえでの自律が重要である」
- 「論理的に言えば、調和は心から生まれなければならない……。調和は大いに信頼に基づいている。力を用いた途端に恐れが生まれる。恐れと信頼は共存できない」
- 「人間の本性は優しさであると言うとき、もちろんそれが100パーセントそうだというわけではない。すべての人間がその本性を持っているが、その本性に反して偽りの行動をする人も多い」
- 「すべての善の根は、善を尊ぶ心という土壌にある」
- 「人生のあらゆる快適さ――良い食べ物、良い住まい、伴侶――を備えていても、悲劇的な状況に直面すれば、人はなお不幸になることがある」
- 「繁栄するためには、人は最初に非常に懸命に働かなければならず、多くの余暇を犠牲にしなければならない」
- 「家庭とは、自分が安らぎを感じ、よく遇される場所である」
- 「道徳的原則を欠けば、人間の人生は無価値となる。道徳的原則、すなわち誠実さは重要な要素である。それを失えば未来はない」
- 「改宗は私の意図ではない。宗教を変えることは容易ではなく、混乱や困難を招くことがある」
- 「この人生における私たちの第一の目的は他者を助けることである。そしてもし助けられないとしても、少なくとも傷つけてはならない」
- 「何かを語ることで強い印象を与えることもあれば、沈黙を守ることで同じように意味深い印象を与えることもある」
- 「自分自身と和解しない限り、外の世界に平和を得ることは決してできない」
- 「私はただの一人の人間にすぎない」
- 「私が西洋を訪れるのは、ほとんどの場合、人間の価値と宗教的調和を促進するためである」
- 「次のダライ・ラマの転生者を誰とするかは、チベットの人々が決定しなければならない」
- 「多くの人々が、私の考えを聞いた後に心がずっと幸せになったと私に語ってくれた」
- 「可能なときにはいつでも親切であれ。それは常に可能である」
- 「宗教や瞑想がなくても生きていくことはできる。しかし人間の愛情なしには生き延びることはできない」
- 「私の主な望みは、いずれ現代の教育の場において、宗教に基づくのではなく、共通の経験と共通の感覚、そして科学的発見に基づいて、思いやりの教育を導入することである」
- 「人生で真の悲劇に出会ったとき、私たちは二つの方法で反応できる。希望を失い自己破壊的な習慣に陥るか、その挑戦を通じて内なる力を見いだすかである。仏陀の教えのおかげで、私は後者の道を選ぶことができた」
- 「政府にはあまり多くのことはできないと思う」
- 「中国政府は、チベットが何世紀にもわたって中国の一部であったと言うよう私に求めている。しかし、たとえ私がその発言をしたとしても、多くの人はただ笑うだけだろう。そして私の発言によって過去の歴史が変わることはない。歴史は歴史である」
- 「私は自らの生涯のうちに再びチベットの地を踏むと確信している」
- 「中国の人々自身が、本当に変化を望んでいる」
- 「宗教的信仰を持っているなら、それはとても良いことであり、そのうえに世俗的な倫理を加えることができる。宗教的信念に倫理を重ねるなら、それもまた良いことである。しかし、宗教に関心のない人々であっても問題はなく、宗教ではなく教育を通じて訓練することができる」
- 「穏やかな心は内なる強さと自信をもたらし、それは健康にとって非常に重要である」
- 「ダライ・ラマに何らかの奇跡的な力があると信じたり考えたりする人がいるならば、それは全くのナンセンスである」
- 「他者を助けることは、祈りの中だけでなく、日常生活においても必要である。もし他者を助けることができないと気づいたなら、少なくとも害を与えることはやめるべきである」
- 「物質的な快適さは精神的な苦しみを鎮めることはできない。よく観察すれば、多くの所有物を持つ人々が必ずしも幸せではないことが分かる。実際、裕福であることはしばしばさらに大きな不安をもたらす」
- 「最も暗い日々の中に希望を見いだし、最も明るい日々には集中を見いだす。私は宇宙を裁かない」
- 「私の主な関心は人々と会うことである。なぜなら、私の最大の使命、最大の関心は、人間の価値、人間の愛情、思いやり、そして宗教間の調和を促進することだからである」
- 「私は本当に、中国や中国の人々には、長い文明の歴史と豊かな文化があると思う」
- 「仏教には、瞑想のように誰もが取り入れられる技法がある」
- 「見た目は絶対的なものに思えるが、現実はそうではなく、すべては相互に依存しており、絶対的ではない。その見方は心の平穏を保つのに非常に役立つ。なぜなら、平穏な心を壊す主な原因は怒りだからである」
- 「自己中心的な態度が過ぎると、孤立を招く。その結果、孤独や恐れ、怒りが生じる。極端な自己中心性は苦しみの源である」
- 「今日ほど、生命が普遍的な責任感によって特徴づけられなければならない時代はない。それは国家と国家、人と人との間だけでなく、人間と他のあらゆる生命との関係にも及ぶべきである」
- 「子どもが生まれるとき、人々はその子が障害を持っていないかと心配する。健康な男の子や子どもが生まれると、人々は短い間だけとても喜ぶ」
- 「60億の人類の中で、問題を引き起こす者はほんの一握りにすぎない」