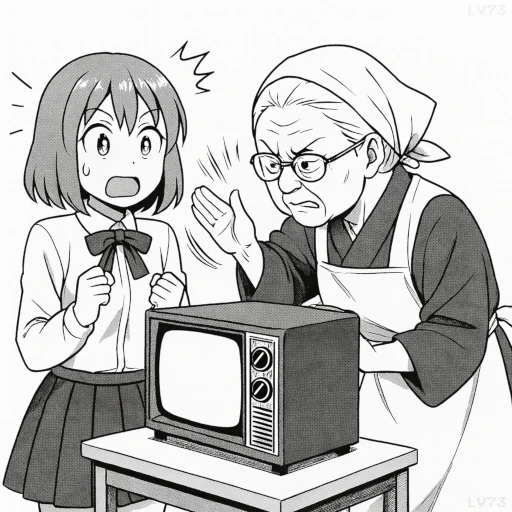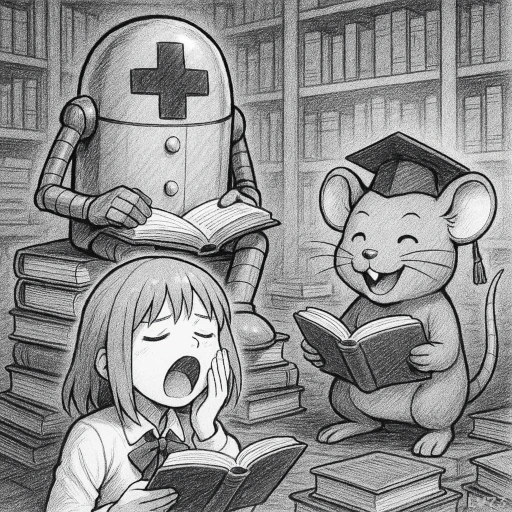「正義なき知識は、知恵ではなく狡猾さと呼ばれるべきである」

- 紀元前427年~紀元前347年
- 古代ギリシアのアテナイ(アテネ)出身
- 哲学者、学者、アカデメイア(アカデミー)創設者
英文
“Knowledge without justice ought to be called cunning rather than wisdom”
日本語訳
「正義なき知識は、知恵ではなく狡猾さと呼ばれるべきである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、知識が正しく用いられなければ、道徳的な価値を持たないというプラトンの考えを示している。知識は、人間が世界を理解し、進歩を遂げるための重要な力だが、それが正義や道徳と結びついていなければ、有害で危険なものとなる可能性がある。プラトンは、知識そのものが善悪の概念と共に使われるべきであり、単に頭の良さや賢さだけでは真の知恵とは言えないと述べている。知識が正義のない形で使われるとき、それは巧妙さや策略にすぎず、人類の幸福には寄与しない。
この考えは、倫理哲学や道徳的価値観の基本的な問題に関わっている。プラトンの哲学では、知識は倫理的な行動と切り離せないものであり、知恵とは「正しく行動する能力」と深く結びついている。もし知識が自己利益のためだけに使われれば、それは他者に害を与える可能性が高くなる。たとえば、詐欺師や犯罪者は高度な知識や技術を持っている場合があるが、その知識は他人を欺くために使われ、社会の善には貢献しない。このように、知識が道徳的な枠組みを持たないとき、それは知恵ではなく狡猾さとみなされる。
現代社会でも、この考え方は広く適用される。科学技術やデータ分析の発展は人類に多くの恩恵をもたらしているが、それが不正や不公平な目的で利用されれば、大きな問題を引き起こす可能性がある。たとえば、個人情報を悪用した詐欺行為や、環境を破壊する技術の使用などが挙げられる。こうした例は、知識が正義のない形で使われるとき、その結果がいかに有害であるかを示している。倫理と知識のバランスがなければ、技術の進歩もまた人類の脅威になり得るという点は、プラトンの言葉が示す重要な教訓である。
「プラトン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!