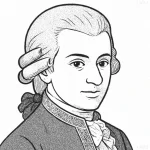「悪を善より好むのは人間の本性ではない。そして、二つの悪から選ばざるを得ないとき、人は少しでも軽い悪を選ぼうとする」

- 紀元前427年~紀元前347年
- 古代ギリシアのアテナイ(アテネ)出身
- 哲学者、学者、アカデメイア(アカデミー)創設者
英文
“To prefer evil to good is not in human nature; and when a man is compelled to choose one of two evils, no one will choose the greater when he might have the less”
日本語訳
「悪を善より好むのは人間の本性ではない。そして、二つの悪から選ばざるを得ないとき、人は少しでも軽い悪を選ぼうとする」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、人間の本質的な倫理観と道徳的選択の傾向を指摘している。プラトンは、人間が本来的に善を求める存在であり、悪を好むことは自然に反していると述べている。たとえ避けられない悪を選ばなければならない場合でも、理性的な判断を下すことが求められ、人は可能な限り被害を少なくする選択をするのだ。これにより、私たちは人間が根本的に悪を嫌い、善を目指して行動する存在であることが理解できる。
この考えは、プラトンの哲学における倫理的理論の一環であり、彼の師であるソクラテスの影響を強く受けている。ソクラテスは、人は善を知ればそれを実行し、悪を選ぶのは無知によるものであると主張した。プラトンはこの思想を継承し、善悪の選択が理性と知識に依存していることを強調する。人間は本質的に善を求める性質を持ち、悪を避ける傾向があるのは、理性が善悪を識別し、より小さな悪を選ぶよう導くからである。
現代社会でも、倫理的なジレンマは多く存在する。たとえば、医療現場では、患者の命を救うためにリスクのある治療法を選ばなければならないことがある。この場合、医師は患者にとって最も被害が少ない方法を選ぶ努力をするだろう。この選択は、人間がいかなる状況でもできる限りの善を目指そうとする本質を表している。私たちの倫理観は、個々の状況に応じて最適な選択をするためのガイドとして機能しており、最も苦しい状況でも理性を用いて判断する力があるのだ。
「プラトン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!