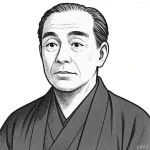福沢諭吉
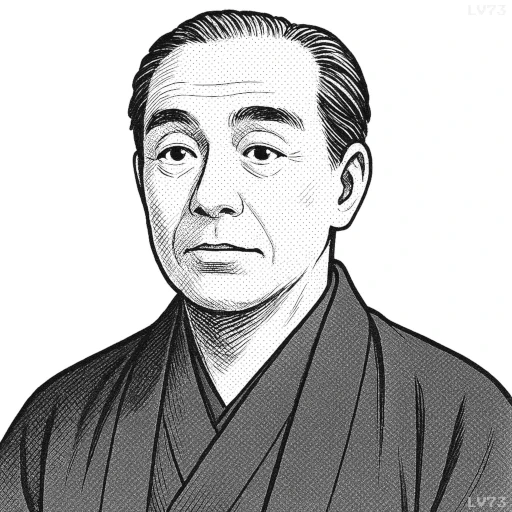
- 1835年1月10日~1901年2月3日(66歳没)
- 日本出身
- 思想家、教育者、著述家、啓蒙運動の先導者、慶應義塾の創設者
人物像と評価
福沢諭吉は、幕末から明治時代にかけて活躍した思想家・啓蒙家・教育者であり、近代日本の精神的基盤を築いた人物である。
彼は「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」の言葉に象徴されるように、個人の独立と平等の重要性を説き、日本における自由主義思想の普及に貢献した。
彼の代表作『学問のすゝめ』は、庶民に向けて学問の意義を説いたもので、教育を通じた国家の近代化という理念を広く浸透させた。
また、慶應義塾を創設し、後の慶應義塾大学へと発展させることで、日本初の私学教育の礎を築いた。
その一方、西洋文明を無批判に受容しすぎたとの批判や、脱亜論に見られるようなアジア諸国への態度には議論の余地もある。
それでも福沢諭吉は、日本の近代国家形成において、思想・教育の両面で絶大な影響を与えた啓蒙の先駆者である。
「いいね」
引用
- 「どれほど西洋を嫌っている者でも、食べ物の好みに関しては攘夷の考えなど持っていない」
- 「まことに善いことをしようとする者は、ただ人情が自然に向かうところをよく見極め、それに従えばよい」
- 「自分を大切にする気持ちを広げて他人にも向け、その苦しみを和らげ幸福を増すよう努めることは、博愛の実践であり、人間の美しい徳である」
- 「親子といっても、親は親、子は子である。だからといって、子のために自分の節操を曲げてまで仕える必要はない」
- 「学者は安逸に満足してはならない。粗末な衣食にも耐え、暑さ寒さを恐れず、米を搗くことも薪を割ることもできなければならない。学問は米を搗きながらでもできるものだ」
- 「学問は、高尚で風雅であるよりも、身近で幅広いものであることが尊い」
- 「学問とは、物事を成し遂げるための技術である。実際の場に接して経験を積まなければ、決して真の勇気や力は生まれない」
- 「神代の水も、華氏212度の熱に達すれば沸騰し、明治の水も同じく沸騰する。西洋の蒸気も東洋の蒸気も、その膨張する力に違いはない」
- 「教育の本質は、人の本来持っていないものを新たに作って与えることではなく、もともと備わっているものをすべて引き出して、何一つ取り残さないようにすることにある」
- 「慶應義塾は一日たりとも休んだことがない。この塾が存在する限り、日本は世界の文明国であり続ける」
- 「下戸が酒屋に入らず、酒好きが餅屋に近づかないようなもので、もし政府が酒屋なら、私は政治という酒が飲めない『下戸』なのです」
- 「志は時代に応じて変えなければならず、主張も情勢に応じて改めなければならない。今の自分と昔の自分がまるで別人のようであってこそ、世の中は進歩していると言えるのだ」
- 「今の自分と昔の自分を比べて、かつての過ちを思い出せば、全身から冷や汗が出るようなことがいくつもある。であれば、軽々しく今の他人を批判すべきではない」
- 「自由とわがままの違いは、他人に迷惑をかけるか否かという一点にある」
- 「柔軟で吸収力の高い子どもにとって、家庭の雰囲気こそが最高の教師である」
- 「『情愛』という言葉の中には、それ自体にある種の無礼さが含まれている」
- 「人間の営みはきわめて複雑で、人生も非常に長い。生涯にわたり無限の人や物、出来事に直面する中で、誤りを避けられる唯一の拠り所は、自分を尊び重んじ、独立した心を持つことである」
- 「心と体の独立をしっかり保ち、自分自身を尊び、人間としての品位を損なわない者こそ、真に『独立自尊』の人である」
- 「人生とは、見るに耐えぬ蛆虫のようなものであり、朝露が乾く間もないほど短く、せいぜい五十年か七十年の間を戯れのように過ぎていくものなのだから、自分の存在を含め、すべての物事を軽く見て、熱中しすぎて生きるべきではない」
- 「人生を戯れと認めつつも、その戯れを真剣に勤め上げて飽きずに続ける。その飽きなさゆえに社会の秩序が保たれると同時に、人生を本来戯れだと知っているからこそ、大きな局面に直面しても動じず、憂えず、後悔せず、悲しまず、心安らかでいられるのである」
- 「世間では圧制的な政府があると言われているが、実はそれは政府の側の問題ではなく、人民の側が圧制を招いているのだ」
- 「そもそも物事を行わせるには、命じるよりも諭すほうがよく、諭すよりも自ら実例を示すほうが優れている」
- 「自然の道理が真実である以上、あらゆる物事の働きには正しい因果関係があることもまた疑いようがない」
- 「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」
- 「人間というものは、まさしく社会という場に生きる『虫』にほかならない」
- 「人間の心は広く果てしないものであり、理屈を超えたところで、ゆったりとした境地に至ることができるものだ」
- 「人間の目的は、ただひとえに文明に到達することにある」
- 「人の情は、昔も今も、どの国でも同じであり、言葉の表現こそ違っても、仁義や五常の教えがまったく存在しない国はない」
- 「博識とは、知識や見聞が広いことであり、善いことだけを知っているという意味ではない。悪いことについても深く理解し、それを行う方法すら知っていながら、君子はあえてそれを行わないだけなのだ」
- 「人と付き合うには、まず信頼をもって接するべきである。自分が人を信じれば、人もまた自分を信じるようになる。人々が互いに信頼し合ってこそ、はじめて自他それぞれの独立自尊を真に実現することができるのだ」
- 「人がいくら多くいても、他者と交わる方法を知らなければ、自分一人しかいないのと同じことであり、世界がいくら広くても、その人情や風俗に通じなければ、自分一人しか世界にいないのと同じである」
- 「人が世の中を生きていく様子を見ると、思っている以上に悪事を行い、予想以上に愚かなことをし、計画していても案外うまくいかないものだ」
- 「人はそれぞれが自分自身のものであり、同時に天下(世の中)は万人に共通するものである」
- 「人が、生まれながらに持つ才能や能力を発揮しようとする際に、心と体の自由を得ていなければ、その才能も能力も役に立たない」
- 「文明は、物事が多く起こる混乱の中でこそ進歩する。出来事が多ければ、多様な勢力が互いに均衡を保つようになるのだ」
- 「水があまりに澄みすぎていると魚が住めないように、人の知恵があまりに明晰すぎると友ができにくい。友人を受け入れるには、度量が広く、少しばかり曖昧さを持つことが必要である」
- 「物に執着し貪るような行為は、真の男のすることではない」
- 「桃太郎が鬼ヶ島へ行ったのは、宝を奪いに行くためだったという。これはとんでもないことではないか。宝は鬼が大切にして保管していたものであり、その宝の持ち主は鬼なのである」
- 「この世に政治を行う優れた人物がいないわけではない。ただ、良い政治のもとで生きるにふさわしい民が少ないだけなのだ」
- 「自分の心に思うことを実行し、決して節操を曲げることがない。これこそが『独立』というものである」
- 「自分が楽しいと思うことは、他人にとってもまた楽しいのだから、他人の楽しみを奪って自分の楽しみを増やしてはならない」
- 「私にとって門閥制度は、まるで親の仇のように憎むべきものでございます」