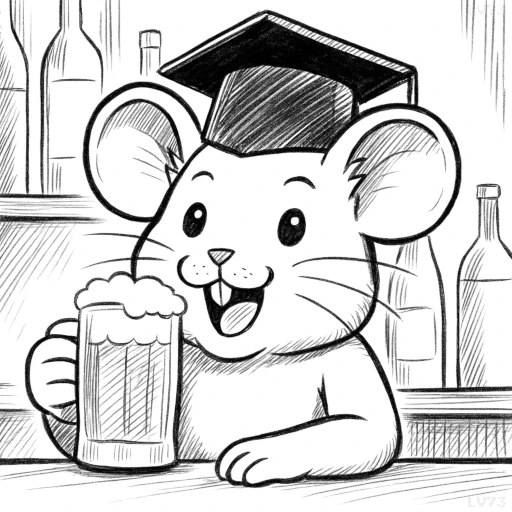「酒に溺れる人は、私の説く道を実行することができない。なぜなら、酒には精神を高ぶらせる作用があり、そのために争いを起こし、言葉や行動を誤るからである」

- 1787年9月4日~1856年11月17日
- 日本出身
- 経世論、農政家、思想家、実践的儒学者
原文
「酒人は我が道を行ふを得ざるなり。何となれば、則ち酒は精神を起すの徳あり。故に諍論を生じ、言行を誤る」
現代語訳
「酒に溺れる人は、私の説く道を実行することができない。なぜなら、酒には精神を高ぶらせる作用があり、そのために争いを起こし、言葉や行動を誤るからである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、節度を失った飲酒が、人の判断力や品性を損ない、道義に基づく生き方を乱すという警句である。尊徳が説いた「道」とは、勤労・誠実・倹約・敬意を重んじる実践的な倫理であり、それを行うには冷静な思考と自制心が欠かせない。ところが、酒は一時的に気を大きくし、感情や行動の節度を奪ってしまうため、「言行を誤る」=口や行動において過ちを犯すのは避けがたいとされる。
実際、尊徳は農村再建や民政の改革を通じて、人々に自律と努力を求めた。そうした中で、酒に溺れれば争いごとが起き、家業は疎かになり、人間関係も破綻することを何度も目にしていたのであろう。ゆえに「酒人は我が道を行ふを得ざる」と断じたのであり、倫理的かつ経済的な安定を妨げるものとしての飲酒に警鐘を鳴らしている。
現代でも、アルコールによるトラブルは多く、飲酒運転、暴言、ハラスメントなど、理性を失った行動が社会的信用や家庭の安定を崩す例は少なくない。尊徳の言葉は、単なる禁酒論ではなく、節度なき享楽は、真に価値ある生き方から人を遠ざけるという普遍的な教えとして、今も深い意味を持っている。
「二宮尊徳」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!