二宮尊徳

- 1787年9月4日~1856年11月17日
- 日本出身
- 経世論、農政家、思想家、実践的儒学者
人物像と評価
二宮尊徳(金次郎または金治郎)は、江戸時代後期の農政家・思想家であり、貧農から身を起こし、多くの荒廃した農村を復興させたことで知られる。
彼の行った報徳仕法は、「勤労・分度・推譲」の三原則を基礎とし、農民に自助努力と道徳心を促しつつ、地域経済の再建を図った。
これは単なる経済政策ではなく、倫理と経済の両立を目指す社会改革思想でもあった。
尊徳はまた、報徳思想という独自の哲学を展開し、「受けた恩に報い、未来に徳を積む」という考えのもと、公共と個人の調和を説いた。
これは後の日本人の倫理観や教育にも多大な影響を与えている。
特に明治以降、勤勉・節約・公共心の象徴として広く顕彰され、小学校の銅像でもおなじみの存在となった。
しかし一方で、彼の教えは封建道徳を強化する側面を持つとも批判され、近代思想との整合性に疑問を呈する声もあった。
それでもなお、二宮尊徳は日本的経済倫理の体現者として、その実践力と影響力において今日でも評価されている。
「いいね」
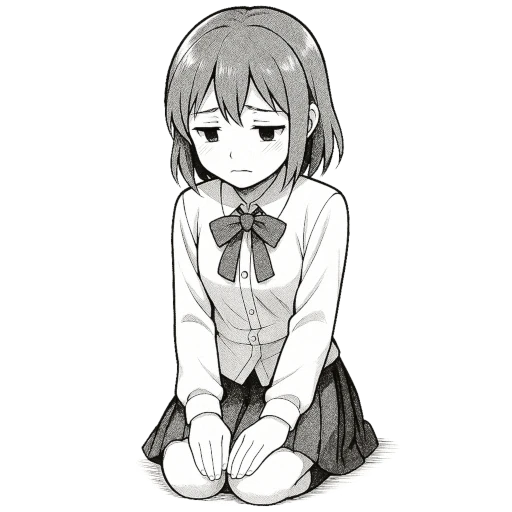
「いいね」が足りない…
引用
- 「おおよそつまらぬ人間というものは、大きなことを望みながら小さなことを怠り、難しいことを心配するばかりで簡単にできることをしない。そのため、結局は大きなことを成し遂げることができない」
- 「家業は精を出して励まなければならないものであり、怠けて済むものではない。欲望はそれとは違い、抑えなければならないものである」
- 「書物とは、人を救う道を記したものである。したがって、それを読んでその心を理解しなければ、何の役に立とうか」
- 「酒に溺れる人は、私の説く道を実行することができない。なぜなら、酒には精神を高ぶらせる作用があり、そのために争いを起こし、言葉や行動を誤るからである」
- 「過去の恩を忘れず、それに報いようとする者は、物事を行えば必ず成功する。過去の恩を忘れ、さらなる恩を欲しがる者は、物事を行えば必ず失敗する」
- 「男でありながら『女大学』を読んで、婦人の道とはこのようなものだと思うのは、とんでもない間違いである。『女大学』は女子のための教訓書であり、貞操の心を鍛えるための書物である」
- 「人の霊的な本質から生まれる心を『真心』といい、それはすなわち『道心』である。身体的な欲望から生まれる心を『私心』といい、それはすなわち『人心』である」
- 「人間が卑しいと見なす動物的な本能の道は、天が定めた自然の道である。人間が尊いとする人の道は、天理にかなってはいるが、人の手による作為の道であり、自然そのものではない」
- 「世の中の人々は、今日飲む酒がなければ借金してまで飲み、今日食べる米がなければまた借りて食べる。これが貧しく困窮する原因である」