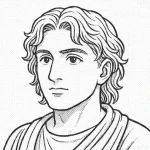「軍隊には適切な範囲の民主主義を実施すべきである。特に、封建的ないじめや体罰の慣習を廃止し、将校と兵士が苦楽を共にするようにすべきである。これが実現すれば、将兵の団結が達成され、軍の戦闘力は大いに高まり、我々が長く苛烈な戦争に耐え抜けることは疑いない」

- 1893年12月26日~1976年9月9日(82歳没)
- 中国出身
- 政治家、思想家
英文
“A proper measure of democracy should be put into effect in the army, chiefly by abolishing the feudal practice of bullying and beating and by having officers and men share weal and woe. Once this is done, unity will be achieved between officers and men, the combat effectiveness of the army will be greatly increased, and there will be no doubt of our ability to sustain the long, cruel war.”
日本語訳
「軍隊には適切な範囲の民主主義を実施すべきである。特に、封建的ないじめや体罰の慣習を廃止し、将校と兵士が苦楽を共にするようにすべきである。これが実現すれば、将兵の団結が達成され、軍の戦闘力は大いに高まり、我々が長く苛烈な戦争に耐え抜けることは疑いない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、毛沢東が紅軍(後の八路軍や人民解放軍)の建軍方針として示した理念を表している。毛沢東は、旧中国軍隊に蔓延していた封建的な上下関係による暴力やいじめを否定し、兵士の主体性を重視する「軍隊の民主化」を唱えた。これにより、兵士と将校の間に信頼と連帯を築き、人民戦争を戦い抜く強靭な軍隊を作ろうとしたのである。
この思想は、従来の軍隊における「上命下服」とは異なり、政治思想教育や将兵一体の生活を重視するものであった。将校が兵士と同じ衣食住を共にし、兵士が発言権を持つ仕組みは、軍の士気を大いに高めた。これが、弱小農村から始まった紅軍が国共内戦や抗日戦争を戦い抜き、最終的に勝利へとつながった重要な要因とされる。
現代においても、この言葉は組織のリーダーシップとメンバーの関係に応用できる。リーダーが特権的に振る舞うのではなく、部下と苦楽を共にする姿勢を示すことで、信頼と団結が生まれる。企業や社会運動においても、上層と下層の距離を縮めることが組織力の強化につながるという教訓として読むことができる。
「毛沢東」の前後の名言へ
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!