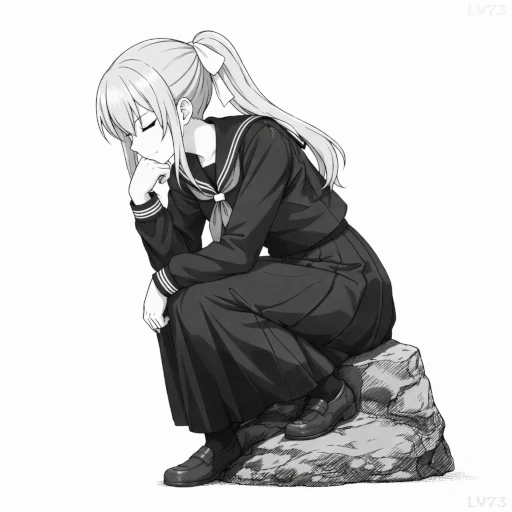「火事はどこか祭礼に似ている」
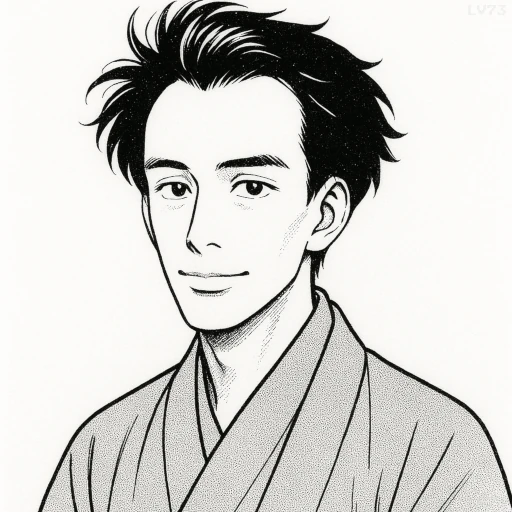
- 1892年3月1日~1927年7月24日
- 日本出身
- 小説家、評論家
原文
「火事はどこか祭礼に似ている」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、災厄と祝祭という本来相反するもののあいだにある共通性を、芥川が鋭く観察した言葉である。火事は本来、人々の生活を脅かす破壊的な出来事であるが、芥川はそこに非日常性・群衆の高揚・視覚的な華やかさといった、祭礼と共通する要素を見出している。つまり、破壊の現場にさえ、人間の集団的な興奮や美的感覚が潜んでいるという逆説が語られているのである。
この言葉には、芥川の持つ都市的感覚と美的冷静さが表れている。彼が生きた大正期の東京は、木造家屋が密集し、火事が頻繁に起こる都市だった。そのたびに人々は、恐怖と同時に好奇心や興奮をもって火事場へ集まった。芥川はそうした現象に、文明の表層の下にある原始的感情――すなわち群衆心理や無意識的な快楽への嗜好を見ていた。火の揺らめき、鐘の音、走る人々――それはまさに都市の「負の祝祭」とも呼べる光景である。
現代においても、この言葉は鋭い意味を持つ。たとえば災害報道や事故現場にカメラを向ける群衆、ネット上で炎上を「見物」する態度など、悲劇に対してすら人はどこかで演劇的・祝祭的に関わってしまう。芥川のこの名言は、人間の感情の複雑さと、日常と非日常の境界が揺らぐ瞬間の本質を、わずか一文で的確に言い表しているのである。
「芥川龍之介」の前後の名言へ
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!