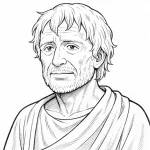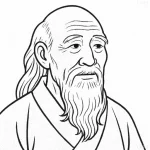「足るを知る人間なんか誰一人いないのが社会で、それでこそ社会は生成発展するのである」

- 1925年1月14日~1970年11月25日
- 日本出身
- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家
原文
「足るを知る人間なんか誰一人いないのが社会で、それでこそ社会は生成発展するのである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、三島由紀夫が社会の本質と人間の欲望について鋭く分析したものである。社会とは、足るを知り満足する人間によってではなく、常に足りないと感じ、もっとを求める人間たちによって動かされ、発展してきたという認識が示されている。ここでは、欲望の尽きなさが社会を変動させ、活力を与えているという逆説的な真理が語られている。
三島は、「足るを知る」ことが個人の徳目としては称賛される一方で、社会という集団の運動においてはむしろ飽くなき欲望こそが不可欠であると見抜いていた。人間が満足せず、さらに高みを求め続けるからこそ、技術も文化も政治も止まることなく推進される。この言葉は、三島が持っていた人間存在に対する冷徹なリアリズムと、社会における欲望の役割への深い洞察を象徴している。
現代においても、この洞察は極めて有効である。たとえば、経済成長や科学技術の進歩も、現状に満足しない人間たちの不断の欲求によって生まれてきた。「足るを知る」ことの美徳を超えて、満たされないことこそが人間と社会の発展を支える動力である。
「三島由紀夫」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!