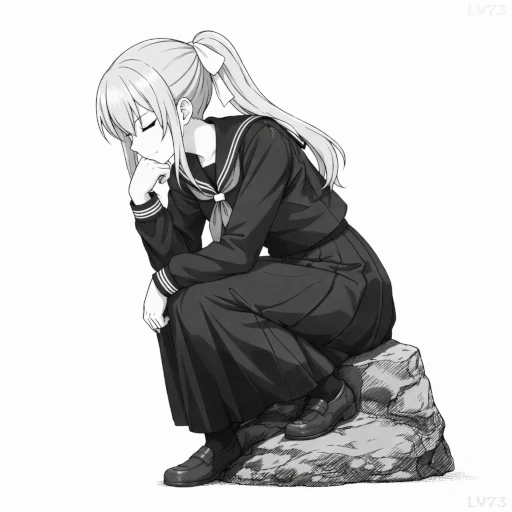「幸福がつかのまだという哲学は、不幸な人間も幸福な人間もどちらも好い気持にさせる力を持っている」

- 1925年1月14日~1970年11月25日
- 日本出身
- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家
原文
「幸福がつかのまだという哲学は、不幸な人間も幸福な人間もどちらも好い気持にさせる力を持っている」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、三島由紀夫が幸福観に対する皮肉と救済の両面を描き出したものである。幸福が本質的に一時的で儚いものであるという哲学は、今まさに幸福を感じている者にはその価値を一層輝かせ、不幸に沈んでいる者にはやがて来る幸福への希望を与える力を持つという認識が示されている。ここでは、幸福と不幸を超えた場所に立つ精神の自由が語られている。
三島は、幸福を固定された永続的な状態と考えるのではなく、つかの間の閃光のようなものと捉えた。この理解は、現実の不安定さを受け入れることで、幸福に対する執着や不幸に対する絶望から解放される道でもある。幸福も不幸もいずれ過ぎ去るものであり、だからこそ一瞬一瞬を深く味わうべきだという、無常観に裏打ちされた肯定的な生き方が示されている。この言葉は、三島が持っていた人生に対する美しく峻厳な態度を象徴している。
現代においても、この洞察は心に響く。たとえば、成功や挫折に一喜一憂する社会のなかで、幸福を絶対視せず、儚いものとして受け止める視点は、人間に深い心の自由をもたらす。幸福も不幸も過ぎゆくものと知ったうえで、今を味わい、生を肯定せよ。
「三島由紀夫」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!