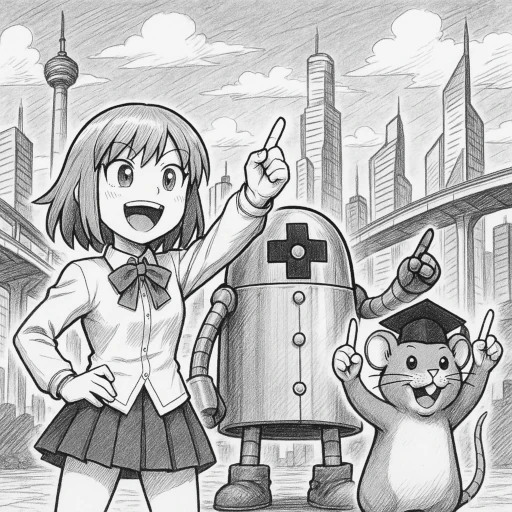「音楽は夢に似ている。と同時に、夢とは反対のもの、一段とたしかな覚醒の状態にも似ている」

- 1925年1月14日~1970年11月25日
- 日本出身
- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家
原文
「音楽は夢に似ている。と同時に、夢とは反対のもの、一段とたしかな覚醒の状態にも似ている」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、三島由紀夫が音楽の二重性を繊細に捉えたものである。音楽は、人間の意識を柔らかく揺さぶり、夢のように非現実的な感覚を呼び起こす一方で、逆に、極度に研ぎ澄まされた覚醒の感覚をもたらすという、相反する二つの性質を併せ持つことが示されている。ここでは、音楽が人間の精神の深層と高次元の意識の両方に触れる特異な芸術であることが語られている。
三島は、芸術一般に対して、現実逃避的な陶酔と、現実を超えた鋭い覚醒という二つの側面を重視していた。彼にとって音楽は、単なる感傷や夢想ではなく、むしろ精神を極限まで高め、現実以上に確かな感覚をもたらすものでもあった。この言葉は、三島が捉えた芸術における陶酔と覚醒、夢と現実の微妙な交錯を象徴している。
現代においても、この洞察は大きな意味を持つ。たとえば、音楽を聴くことで現実を忘れるような没入感を得ると同時に、逆に生の感覚が鋭くなる瞬間を体験することは、多くの人にとって共通の経験である。三島のこの言葉は、音楽が単なる逃避ではなく、人間の意識を深く覚醒させる力を持つことを示し、芸術体験の豊かさと複雑さを静かに、しかし力強く教えているのである。
「三島由紀夫」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!