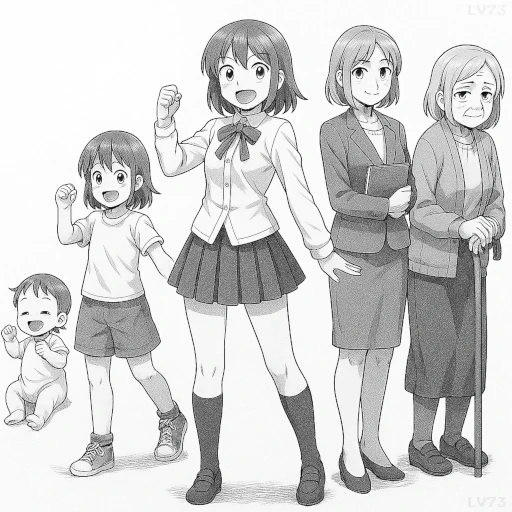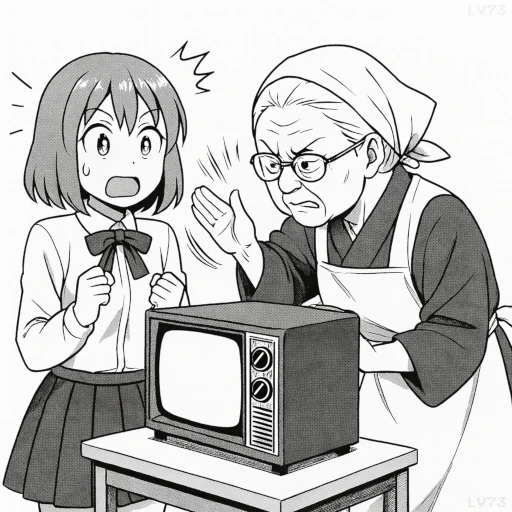「お節介は人生の衛生術の一つです」

- 1925年1月14日~1970年11月25日
- 日本出身
- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家
原文
「お節介は人生の衛生術の一つです」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、三島由紀夫がお節介という行為に肯定的な意義を見出したものである。通常は煩わしいものとされがちな「お節介」も、実は人間関係の停滞や腐敗を防ぐための一種の衛生術、つまり社会的な清掃活動のような役割を果たしているという認識が示されている。ここでは、人と人との距離を適度に保ちつつ、関係を活性化させる機能としてのお節介の価値が語られている。
三島は、人間関係において孤立や無関心がもたらす精神の荒廃や虚無感を強く懸念していた。戦後社会の個人主義が進む中で、互いに干渉し合わないことが美徳とされる風潮に対して、彼は人間同士が関与し、注意を払い合うことの重要性を訴えた。この言葉は、三島が考える人間関係の健全さを保つための積極的な働きかけを肯定するものであり、単なる煩わしさではなく生きる上での必要な技術としてお節介を位置づけている。
現代においても、この指摘は意義深い。たとえば、プライバシーや自立が重視されるあまり、誰も他人に手を差し伸べず、無関心が支配する社会が生まれつつある中で、三島のこの言葉は、適度なお節介が人間関係を潤滑にし、社会全体の健康を保つ役割を果たすという真実を静かに、しかし力強く教えているのである。
「三島由紀夫」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!