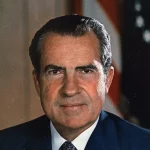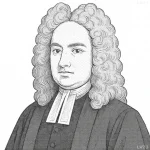「常に奉公人は、主君から預かった物を適切に使い、余らせてはならない。余らせることは盗みである。使いすぎて借金をするのは愚か者である」

- 1560年頃~1600年10月21日
- 日本(戦国時代・近江国)出身
- 武将、奉行、政治家
原文
「常に奉公人は主君より取物を遣ひ合せて、残すべからず。残すは盗なり。つかひ過して借銭するは愚人なり」
現代語訳
「常に奉公人は、主君から預かった物を適切に使い、余らせてはならない。余らせることは盗みである。使いすぎて借金をするのは愚か者である」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、主従関係における奉公人の心得を厳しく戒めたものである。石田三成は豊臣政権下で財政管理を任され、細やかで厳格な態度で知られていた。主君から与えられた資源は、必要な分だけを正しく使うべきであり、「残す」ことも「使いすぎる」ことも、どちらも忠義に反する行為であると明確に断じている。
安土桃山時代は、領地や俸禄の配分が重要な統治手段であり、財務管理は政権運営に直結していた。「残すは盗なり」という厳しい断定は、主君の意図を無視する行為は重大な背信行為であるとの認識を示す。また、使い過ぎによる借財は、主君に対する迷惑だけでなく、組織全体の信用を損なうものとされた。三成の律義さと、主君への徹底した忠誠心がうかがえる。
現代においても、資源管理や予算運営における適正使用の大切さを強く示唆する言葉である。たとえば、企業において与えられた経費を適切に使い切り、無駄も不足も生じさせないことが、組織人としての責任である。任された資源を「いかに正確に、誠実に使うか」という意識は、時代を越えて求められる資質である。
「石田三成」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!