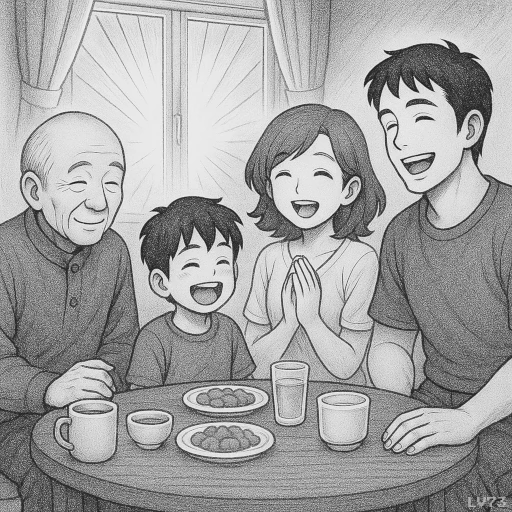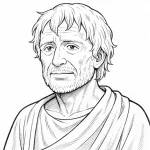「大家族を育てる者は、確かに生きている間、より多くの悲しみにさらされる的となる。だが同時に、より多くの喜びにもさらされる的となるのだ」

- 1706年1月17日~1790年4月17日
- アメリカ合衆国出身
- 政治家、発明家、科学者、著述家
英文
“He that raises a large family does, indeed, while he lives to observe them, stand a broader mark for sorrow; but then he stands a broader mark for pleasure too.”
日本語訳
「大家族を育てる者は、確かに生きている間、より多くの悲しみにさらされる的となる。だが同時に、より多くの喜びにもさらされる的となるのだ」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、多くの子を育てる人生の中にある苦しみと喜び、その両面を認める成熟した感受性を表している。ベンジャミン・フランクリンは、家族や社会の中で生きる人間の姿を現実的に見つめ、大家族を持つことは喜びの源であると同時に、心を痛める機会も多くなるという真理を受け入れていた。この言葉は、人生の豊かさは安定だけでなく、変化や不確実性とともにあるという教訓をやさしく語っている。
現代においても、家族は幸福や支えの象徴である一方で、病気、死別、経済的負担、人間関係の摩擦など、避けられない多くの試練と向き合う場でもある。この名言は、そうした現実を否定せず、多くを愛し、関わるということは、それだけ多くの感情の波に包まれることなのだと教えてくれる。そしてその分だけ、人生が深く、豊かになることを肯定している。
この言葉にはまた、苦しみと喜びは表裏一体であり、どちらかを避ければもう一方も遠ざかるという、深い人生観が込められている。フランクリンは、人間の幸福とは安逸の中にあるのではなく、関わり合いと感情の交流の中にこそ宿ると信じていた。「広い的」は不安定かもしれないが、それは同時に、より多くの愛と感動に心を開いているということ――この一文は、人生の本質を見つめる穏やかで力強い肯定の言葉である。
「ベンジャミン・フランクリン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!