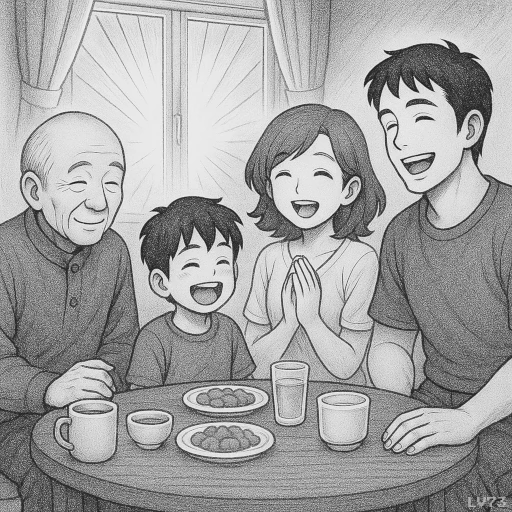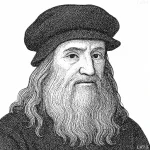「妻を迎えるのは、家(と暖炉)が備わってからにせよ」

- 1706年1月17日~1790年4月17日
- アメリカ合衆国出身
- 政治家、発明家、科学者、著述家
英文
“Never take a wife till thou hast a house (and a fire) to put her in.”
日本語訳
「妻を迎えるのは、家(と暖炉)が備わってからにせよ」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、家庭を築く前に、まずは生活の基盤を整えるべきだという現実的かつ倫理的な教えである。ベンジャミン・フランクリンは、恋愛や結婚に対しても感情だけで動くのではなく、責任と準備を伴う人生の一大事として捉えていた。ここで「家」と「暖炉」は、住居と生活の安定(経済的・物理的な備え)を象徴しており、結婚とは感情だけでなく実務的な準備があって初めて成り立つものであるという考えが表れている。
現代においても、結婚を考える際には、経済力や住環境、生活設計の現実性が大きな要素となる。愛情だけで成り立つ結婚は理想的に聞こえるが、生活の基盤が不安定であれば、やがて関係自体も困難に直面することは多い。この名言は、愛と責任を両立させるためには、まず自立と準備が欠かせないという、人生設計における重要な原則を語っている。
この言葉は、結婚を人生の成熟の証と捉え、そのためにはまず土台を築くことが大切であるというメッセージを伝えている。フランクリンの考えは、感情に流されるのではなく、理性と覚悟をもって人生のパートナーを迎えるべきだという姿勢を示しており、愛は備えと共にあってこそ持続し、深まるという真理をこの一文に込めている。
「ベンジャミン・フランクリン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!