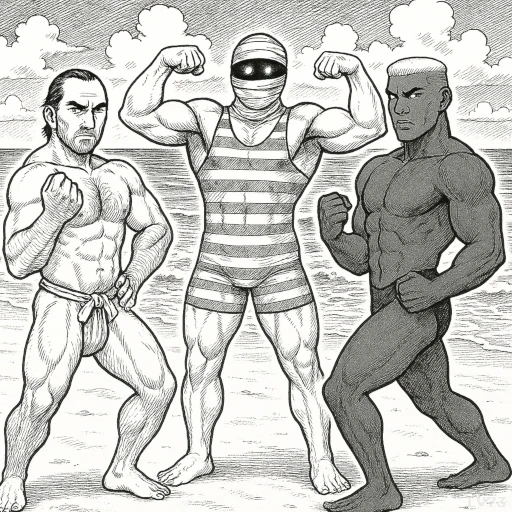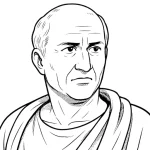「敵に対して怒るべきだと言い、それを偉大で男らしいことと考える者たちの声に耳を貸してはならない。最も称賛に値し、最も高貴で偉大な魂を示すものは、寛容と許しの心である」

- 紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
- ローマ共和国出身
- 政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
英文
”Let us not listen to those who think we ought to be angry with our enemies, and who believe this to be great and manly. Nothing is so praiseworthy, nothing so clearly shows a great and noble soul, as clemency and readiness to forgive.”
日本語訳
「敵に対して怒るべきだと言い、それを偉大で男らしいことと考える者たちの声に耳を貸してはならない。最も称賛に値し、最も高貴で偉大な魂を示すものは、寛容と許しの心である」
解説
この言葉は、敵に対して怒りや報復で応じるのではなく、寛容と許しによって対応することこそが、真に偉大な人格の証であるというキケロの倫理的信条を力強く示した格言である。彼は、怒りや復讐心は一見して強さの表れのように見えるが、実際には感情に支配された未熟さであり、真の力は理性と節度に根ざした寛容さにあると考えた。つまり、赦すことのできる者こそが、もっとも気高く、賢明であるという逆説的真理がこの言葉に込められている。
この考えは、キケロが『義務について(De Officiis)』で繰り返し述べる「慈悲(clementia)」の徳と一致しており、権力を持つ者ほど復讐よりも赦しを選ぶべきであると強調する姿勢が貫かれている。特に政治や法の場面においては、感情的対応ではなく、理性的で節度ある裁きが国家の安定と尊敬を保つとされた。キケロにとって、怒りは衝動であり、赦しは理性と品位の表現である。
現代においてもこの格言は、対立と和解の問題、個人間の関係、さらには国際外交に至るまで広範な応用を持つ。報復を称賛する風潮が時に支配的になる中で、赦す勇気と寛容の姿勢が社会的・道徳的成熟の指標として再評価されている。キケロのこの言葉は、怒りや力ではなく、赦しと理解こそが真の高貴さを示すものであるという、時代を超えた倫理の理想を静かに語る名言である。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?