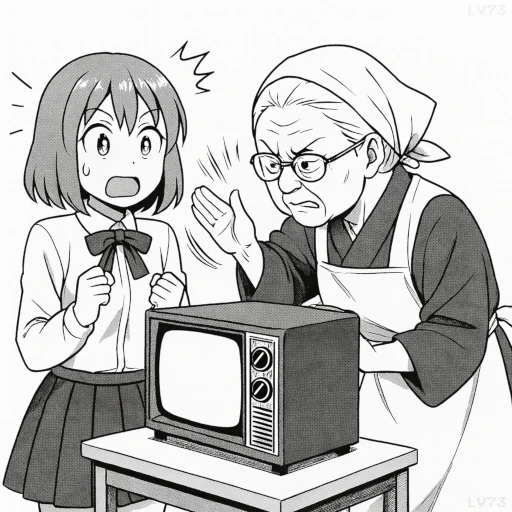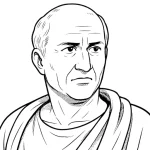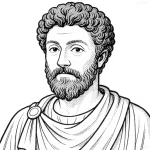「弁論家は、自らの主張が弱いときに最も激しく語るものである」

- 紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
- ローマ共和国出身
- 政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
英文
“Orators are most vehement when their cause is weak.”
日本語訳
「弁論家は、自らの主張が弱いときに最も激しく語るものである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、説得力のない主張を覆い隠すために、弁論家が感情や声量に訴えるという逆説的な現象を皮肉ったキケロの鋭い観察である。彼は、真に強い論理や証拠を持つ主張は、静かで理性的に語っても十分に伝わるが、根拠の乏しい主張は、しばしば激しい語調や誇張された修辞によって正当化されようとすると述べている。つまり、雄弁さの激しさは必ずしも論の強さを意味しないという、表現と内容の乖離に対する警告が込められている。
この格言は、キケロの著作『弁論家について(De Oratore)』や『話し方について(Orator)』で展開される、弁論術における内容と形式の関係に関する考察とも一致する。彼は、感情表現(パトス)や語りの技巧が重要であることを認めつつも、それが論理(ロゴス)と結びついて初めて価値を持つと強調した。論が弱いときに強い表現に頼ることは、説得ではなく印象操作に陥る危険があると指摘している。
現代においてもこの格言は、政治的演説、広告、討論など、あらゆる説得の場面で通用する。声高な主張や感情的な演説がなされているときほど、冷静にその中身を吟味する必要がある。特に、論拠や事実に乏しい主張が、怒りや恐怖といった感情で補強されていないかを見抜く力が求められる。キケロのこの言葉は、「何を語るか」ではなく「どのように語っているか」に惑わされず、本質を見極める理性の重要性を教える、普遍的な知的警句である。
「キケロ」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!