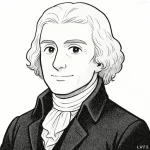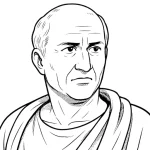「雄弁さと慎みを兼ね備えて語る弁論家には、大いなる敬意を抱かざるを得ない」

- 紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
- ローマ共和国出身
- 政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
英文
“Great is our admiration of the orator who speaks with fluency and discretion.”
日本語訳
「雄弁さと慎みを兼ね備えて語る弁論家には、大いなる敬意を抱かざるを得ない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、言葉の巧みさ(fluency)と慎重な判断力(discretion)の両方を備えた弁論家こそ、真に称賛されるべき存在であるというキケロの弁論観を表している。彼は、単に話が上手なだけでは不十分であり、その言葉が状況や道義、聴衆に対する深い配慮に裏打ちされてこそ、真の雄弁となると考えた。つまり、技術と倫理の両立が、弁論における真の価値を生むのである。
この思想は、キケロの代表作『弁論家について(De Oratore)』に詳しく展開されており、理想の弁論家とは、知識・判断・道徳・表現力の全てを兼ね備えた「賢者」であるとされている。彼は、弁論術が単なる技巧ではなく、正義と公益のために用いられるべきであると強く主張し、聴衆を欺くのではなく導くための言葉こそが、真の雄弁であると説いた。
現代においてもこの言葉は説得力を持つ。政治家、教育者、報道者など、言葉によって人々に影響を与える立場の者にとって、流暢さと同時に慎重さ、つまり言葉の責任を自覚する姿勢が求められる。たとえば、熱弁をふるう者でも、その言葉に節度と誠実さがなければ信頼を得ることはできない。キケロのこの格言は、言葉を用いる者の品格と節度がいかに大切であるかを教える、普遍的な倫理の表明である。
「キケロ」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!