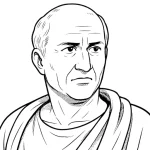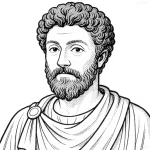「偽りとは、真実の模倣にすぎない」

- 紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
- ローマ共和国出身
- 政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
英文
“The false is nothing but an imitation of the true.”
日本語訳
「偽りとは、真実の模倣にすぎない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、偽り(虚偽)というものが単独で存在するのではなく、常に真実の形を模倣することで成り立っているという、キケロの哲学的認識を表している。彼は、虚偽が信じられるのは、それが一見して真実らしく見えるからであり、偽りとは真実の影に過ぎないと考えた。つまり、虚構や欺瞞は真実の存在を前提にして初めて成立する二次的な現象なのである。
この考え方は、キケロが重視した倫理・弁論術・法哲学のいずれにおいても重要な原理である。法廷弁論や政治討論の場では、偽りがしばしば「真実らしさ」をまとって提示されるが、それが本質的に空虚であることを見抜くためには、真実の構造と本質を深く理解する必要がある。キケロは、虚偽を暴く力とは、何よりも真実の本質に精通する知性にあると信じていた。
現代においてもこの言葉は警句として有効である。フェイクニュース、詐欺広告、偽装表示など、現代の多くの偽りもまた「真実のように見えること」で人を惑わせる。AIによる偽情報の生成やディープフェイクの登場により、「真実らしさ」と「真実」の区別がますます困難になっている時代において、キケロのこの言葉は、真理を基準とする洞察力の重要性と、虚偽の本質的な依存性を明確に示す倫理的指針となる。
「キケロ」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!