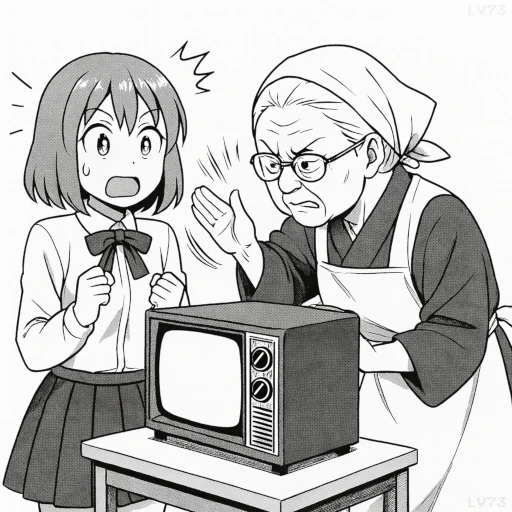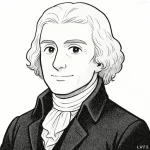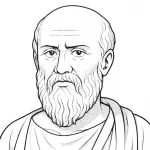「雄弁家は内容の深さに欠ける分を、話の長さで補おうとする」

- 1689年1月18日~1755年2月10日
- フランス王国出身
- 哲学者、法学者、政治思想家
英文
“What orators lack in depth they make up for in length.”
日本語訳
「雄弁家は内容の深さに欠ける分を、話の長さで補おうとする」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、雄弁や演説が必ずしも内容の充実を伴っているわけではなく、しばしば冗長さで飾り立てられていることへの鋭い皮肉である。モンテスキューはここで、話し手が本質的な中身や論理の深さを持たないとき、形式や長さに頼って聴衆を圧倒しようとする傾向を批判している。つまり、量で質をごまかす言葉の過剰を、知性に欠ける者の常套手段として見抜いているのである。
この言葉は、啓蒙時代における理性と明晰さを重んじる思想の一部として位置づけられる。モンテスキューをはじめとする多くの啓蒙思想家たちは、簡潔かつ明瞭な論理こそが真の説得力であると信じており、空疎なレトリックや修辞に頼る長広舌を軽蔑していた。この名言は、説得における「中身」と「表現」のバランスがいかに大切かを示す批判的観察である。
現代においても、政治家や評論家、インフルエンサーなどの発信において、話の長さに比して内容が伴わない例は多く見られる。この名言は、本質を語る者は簡潔であり、言葉数が多いからといって賢明とは限らないという、聞き手に対する知的警告である。言葉の重みは、その量ではなく、そこに宿る意味と構造によって測られる。
「モンテスキュー」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!