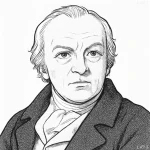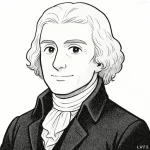「人の死ではなく、その誕生にこそ涙が注がれるべきである」

- 1689年1月18日~1755年2月10日
- フランス王国出身
- 哲学者、法学者、政治思想家
英文
“There should be weeping at a man’s birth, not at his death.”
日本語訳
「人の死ではなく、その誕生にこそ涙が注がれるべきである」
解説
この名言は、人生に待ち受ける苦難や不条理を予期する視点から、誕生の瞬間こそが最も悲しむべき出来事であるとする、哲学的で厭世的な逆説を提示している。モンテスキューは、死が苦しみの終焉であり、むしろ安らぎの到来であると見なす一方で、誕生は人間がこれから耐えねばならない試練の始まりだと捉えている。
この思想は、彼が18世紀という政治的・社会的不安定な時代を生きた啓蒙思想家であることと無関係ではない。モンテスキューは権力の腐敗、戦争、抑圧、不平等といった人間社会の現実に深い洞察を持っており、そうした世界に新たに足を踏み入れること自体が憂うべきことであると考えた。この名言には、死を悲劇ではなく解放と捉える死生観と、生に対する批判的まなざしが込められている。
現代においても、生きることの意味や価値が不安定化する社会では、この名言が投げかける問いはなお重要である。それは単に生を否定する言葉ではなく、人間が生まれた瞬間から背負う宿命と責任、そして苦しみの可能性を自覚せよという倫理的警告でもある。生の価値を深く考え、軽々しく祝福するのではなく、より慎重に、敬意をもって迎えよというメッセージが読み取れる。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「モンテスキュー」の前後の名言へ
関連するタグのコンテンツ
死
申し込む
0 Comments
最も古い