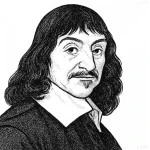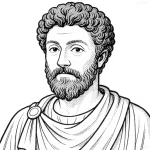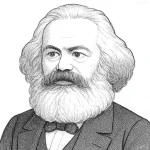「宗教は虐げられた者のため息であり、無情な世界の中の心であり、無魂の状況の中の魂である。それは民衆のアヘンである」

- 1818年5月5日~1883年3月14日
- プロイセン王国(ドイツ)出身
- 哲学者、経済学者、政治思想家
英文
“Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.”
日本語訳
「宗教は虐げられた者のため息であり、無情な世界の中の心であり、無魂の状況の中の魂である。それは民衆のアヘンである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、カール・マルクスが宗教の役割とその影響について述べた有名な表現である。彼は、宗教が抑圧された人々にとっての慰めであり、厳しい現実から逃避する手段として機能していると指摘している。宗教は「心」や「魂」のような役割を果たし、過酷な環境にいる人々に希望と安心感を与えるが、それは一時的な救済でしかなく、根本的な解放にはつながらないと批判している。
現代においても、この見解は宗教が持つ慰めと現実逃避の二面性について考えさせられる。宗教が個人に精神的な支えを与える一方で、社会の不平等や抑圧を隠す手段として利用されることもある。マルクスの視点では、宗教が人々を慰めることで本質的な変革の意欲を失わせ、現状維持を助長しているとされ、彼は宗教の影響が労働者階級の解放を妨げると考えた。
具体例として、歴史的に宗教が社会的な抑圧の道具として使われ、既存の権力構造を正当化してきたケースが挙げられる。たとえば、貧困や不平等が「神の意志」として受け入れられることで、抑圧された人々が自らの状況を変えようとする意欲が削がれることがある。このように、マルクスは宗教が社会に安定をもたらす一方で、人々が現実の改善を求める動きを抑制する側面を強調している。彼のこの言葉は、宗教の本質的な役割とその影響力について深い考察を促すものである。
「マルクス」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!